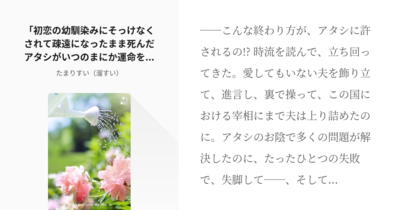たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 3492 posts · Server pawoo.net
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 3492 posts · Server pawoo.net
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 3445 posts · Server pawoo.net「初恋の幼馴染みにそっけなくされて疎遠になったまま事故で死んだアタシがいつのまにかあの街に引っ越してきたその日に戻っていた?!」
ジャクヴィル公爵家はーじまるよー
――こんな終わり方が、アタシに許されるの!?
時流を読んで、立ち回ってきた。愛してもいない夫を飾り立て、進言し、裏で操って、この国における宰相にまで夫は上り詰めたのに。アタシのお陰で多くの問題が解決したのに、たったひとつの失敗で、失脚して――、そして――。
「おまえは魔女だ!」
その怒鳴り声と共に鋭い銀線が走って――………………。
***
「おい、大丈夫か」
「……!」
ぱっと飛び起きてヴィルは目を瞬かせた。さっきまで取り囲んでいた兵隊たちはいないし、燃えさかる炎も見えない。見えたのは心配そうに、きかん気の強そうな顔を寄せてくるジャック、そして高く澄んだ青空だった。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1994 posts · Server pawoo.netタマムイのあとに書いていた二本です。
恋のコスメティックス……ジャックほどアタシをかわいく見せる化粧品はない。
真昼の星……見えなくても導いてくれる。それがアンタでしょ?
恋のコスメティックス/真昼の星・ジャクヴィル | たまりすい(溜すい) #pixiv https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19660192 #ジャクヴィル
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1994 posts · Server pawoo.netヴィル様誕生日おめでとうございます!
ブルームな箒に一本だけバラを忍ばせるジャックくん、いたらいいなと思って……。
ジャックくんはヴィル様を喜ばせる天才ですね!
祝福と癒やしをあなたに・ジャクヴィル | たまりすい(溜すい) #pixiv https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19660120 #ジャクヴィル
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1396 posts · Server pawoo.net なんでですか、と小首をかしげるジャックに、ヴィルは鋭い目をくれる。
「皆まで言わせないでちょうだい。明日までの宿題よ」
――アンタはアタシの道標。精神的に迷ったときの、道標、なんて言ったところで、いまのジャックには響くまい。どんな素敵な言葉でも言うべきタイミングというものがあるのだ。それもジャックが教えてくれたような気がする。
「さ、アンタは他の部員の応援に行きなさい。それが礼儀よ。アタシは帰る」
「はい! 明日までに宿題を解いてみせます」
「言っておくけど、誰かに訊いてはダメよ。自分ひとりで考えなさい」
そう言ってヴィルはジャックの背を叩き、競技場を後にする。明日のジャックの答えを楽しみに待ちながら。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1396 posts · Server pawoo.net「そうっすね」
「星は明るいと見えない。でも確かにある。暗くなったら誰にでも見える。分かる?」
「すいません、全然です」
抽象的な話があまり得意でない幼馴染みは頭を振った。仕方ない、今日はサービズだとヴィルはこう説明した。
「人には相応しい舞台があって、その舞台でこそ輝くってことよ。……アタシはアンタの学校では浮いてたけど、アンタの前では輝いてた。そうでしょ」
ジャックは覚えていなさそうだが、ヴィルのことを『昼間の星』だと例えたのは彼だ。言われた当時は腹が立って、三日ほど口を利かなかった――太陽に負けている、と言われたような気がしたからだ――。ジャックなりに『昼夜問わず輝いている』と言いたかったのだと分かったのは、ナイトレイブンカレッジに入ってからだった。
「ヴィル先輩はいつでも輝いてたっす。眩しかった」
「アタシにとってもアンタはそういうもの。あ、いえ……北極星かしら」
「俺が北極星?」
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1396 posts · Server pawoo.net めずらしく朝から夕方まで身体が空いて、ジャックを予選から応援できると胸ときめかせていただけにがっかりではあった。この気持ちに乗って、「残念だったわね」と声をかけるのは容易い。だがジャックはそういう慰めを求めてはしない。ヴィルはやれやれと控え室をノックした。返事が間を置いてあった。
「……誰だ……、ってヴィル先輩っ!?」
「ご自慢の鼻も敗退の前には効かない?」とヴィルが皮肉めかせて言えばジャックは頬を掻いた。ちょうど着替えて帰るところだったらしい。部員の応援をして帰れと言いたくなるのをぐっと堪えてヴィルはこう言った。
「力みすぎ、アタシに良いところ見せようと思ったでしょ」
「……えぇ」
ぼそっとジャックは言ってうな垂れた。
「ちょっと来なさい」
「はい……?」
説教か、という疑いをジャックの返事は含んでいたが、ヴィルは無視した。説教など趣味ではない。周りのジャガイモを育てるためにいつの間にか身についたことだった。
「空、見て」
「……青いっすね。白い点も見える」
「それ星よ。アンタが見えるって自慢してたわね、昔」
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
9 followers · 1396 posts · Server pawoo.net【真昼の星・ジャクヴィル】
――五十メートル走、予選敗退。
ジャックにとって衝撃的だったこの結果は、ヴィルにとっても意外だった。前日、『表彰台のてっぺんに立ちますから』と言い切った幼馴染みは、はったりや嘘を言うタイプではない。確証があって断言する。ジャックがそう言ったからには、彼なりに勝つ確証があったのだろう。
その意気込みがよくなかったのか、ジャックはスタートでフライングを初戦で一度した。その後無事スタートは切れ、二回戦に勝ち上がった。しかしここでフライングを二回、すなわち予選敗退――、優勝候補の筆頭だっただけに内外の驚きは相当なものだった。
この地方大会は、次に続く全国大会の肩慣らしという位置づけで、ここでの結果如何で全国大会の出場の有無が決まるではないが、大事な試合、らしい。
『アタシの仕事で言えば、ドラマかしらね』
ドラマの出来ひとつで次の出演依頼が来るわけではない。しかしあんまりな出来なら倦厭される。
『……今日は決勝まで見れる予定だったのに』
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
10 followers · 1238 posts · Server pawoo.netまあそれもそのはずで、輝石の国は美観の維持のため、特定のエリアにおいて建物の増改築には非常にやかましい。その結果、ジャックは近代になっても見た目は何世代前という家に住んでいた。ヴィルが住んでいた家も古い洋館を住みやすく内装を改良しただけだった。だからこそ、ヴィルがそのエリア外に持つ家は鋭角的で近代的なデザインで、一度招かれていき、ぎょっとした覚えがある。
「ここですかね?」
だらだらと運転すること一時間。
ようやくたどり着いた目的地に立って、ジャックは片眉を上げた。
――石造りの門が崩れている。
それどころか、塀も崩れ、蔦がはびこり、まるで落城後のようだ。ここですか、と問うように目を投げれば、ヴィルはさっさと門をくぐって小道――であったもの――を草をかき分けて突き進んでいた。ジャックはその後を急いで追いかけたのだった。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
10 followers · 1238 posts · Server pawoo.net車はあるから、とヴィルが目で指した先には、のどかな田舎にぴったりな古くさい自動車が止まっていた。見た目はぼろっちいが、きっと中身は最新だろう。ジャックは二つ返事で車に乗り込み、助手席にヴィルが座ることを誇らしげに思いつつ車を発進させた。
そして知る。
ヴィルが芸能人であることを一切隠さなかったのは、ここでは隠す必要ないのだ。
すれ違う車はトラックばかりで(東洋の有名な自動車メーカーのものだ)、道行く人々も古ぼけたデザインの車には目をくれず、自分の向かう方向にしっかりと目を向けていた。横を向けば世界的有名モデルが微笑んでいるとも知らずに。
「ナビだとこっちですが、合ってます?」
「ええ」ヴィルの声はうっとりとしていた。ここの風景を楽しんでいるのだろう。実際、運転しているジャックもこの風景を楽しんでいた。穏やかで柔らかい赤茶色の大地が地平線まで続き、パッチワークのように果実園が広がっている。合間合間に古風な、頑丈な作りのグレイッシュな家があって、それがまたいいアクセントになっていた。ここで車を走らせていると、中世あたりに戻ったような気がする。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
10 followers · 1238 posts · Server pawoo.net 中心地から、電車で三時間。
箒に乗ればもっと短縮できるが、こんな田舎でも箒飛行禁止令は出ている。何のために習得したのやら、と待ち合わせの駅でジャックは首を捻ってから空を見上げた。初夏の終わりを示すような真っ青な空に、オレンジの大地がよく映える。遠くまで果実園と薬草園がつづき、ほのかに芳しい匂いさえ漂ってくる。輝石の国でも随一の美しさをほこるマグヌス・ノースエリアだが、冬の厳しさも群を抜く。その差が美味い果実を生み出すのだと学校で習った覚えがある。
本来なら、今日はトレーニングの日だった。自主トレというヤツだ。マジフトのオフシーズンと言えば身体作りだが、昨年の不振もあり、こうやって気晴らしに田舎にくるのもいいだろう。気晴らしにヴィルを使うのは気が咎めたものの、本人からの誘いだ。問題はあるまい。
「空を見上げてつまんなさそうな顔をしないの。私有地なら飛べるわよ」とヴィルが言った。薄手のシャツに麻のパンツという軽装だが一目で洒落者だと分かる恰好にジャックは苦笑した。芸能人であることを隠すつもりはないらしい。
「アンタ、免許持ってたでしょ? 車を運転してちょうだい」
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
10 followers · 1238 posts · Server pawoo.net「で、アンタに来て欲しいの。来週、見に行くから」
「実物は見てないですか?」
「いいえ。見ずに買うほど愚かじゃないわ。去年見たの。でも今年は見てないから。たぶん、もっと屋敷は荒れてるわ。でも素適なところよ? 温室もあるし、畑もあって、小さな薬品調合室まであるの」
「スゲエ! でもそんなに広いなら男手がたくさん要りますね。業者を呼んだ方がいいのでは?」
専門の知識が要る修繕もあるだろう。そうなるとジャックの努力の範囲を超える、と返答すれば、ヴィルはきっぱりと言った。
「いいえ。アンタとふたりでやるの。ここまで言えば分かるんじゃないの?」
じゃ、返事はあっちで聞かせてね、と電話が切れた。ジャックが来ると信じて止まない声だった。そして好都合なまでにその前後は空いていた。一日どころか三日は手伝えそうだ。でも何の返事を聞かせればいいのかは分からなかった。
「……訊けばいいか、直接」
この間抜け、と鼻先を弾かれそうだが、分からなければ訊くより他ない。これがレオナに褒められた自分の長所だとも思うから。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
10 followers · 1238 posts · Server pawoo.netニュー・ノスタルジック
#ジャクヴィル
「輝石の国に家を買ったの。土地付きでね」
そしてヴィルはとある地名を告げた。輝石の国でも山のほうの農村だ。ジャックは親族がそちらに土地を持っていて、幼い頃に何度か遊びに行ったが、子供心にも美しいところだと思っていた。しかしヴィルが好むような賑やかな土地ではない。どちらかと言えばのんびりとした空気を楽しむ場所だ。そうジャックが答えたらヴィルが電話の先でクスクスと笑った。
「そうよ、察しが良いじゃない。別荘なの。世界中の観光地を巡って決めた。あの土地がいいっって」
「でも輝石の国なんですね」
「ええ。あちこち見て回っての結論よ。それに輝石の国ならアンタも来やすいでしょ」
「それはそうですが」どきりとした。自分のことを考えて買うとは思わなかったからだ。ヴィルの声がおかしそうに踊った。
「何驚いた声を出してるのよ。アンタのことを考慮しなかったことってないのよ。アンタと出会ってから」
ものすごい告白をされた気もしたが、次の実務的な相談でそれも吹き飛んだ。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
7 followers · 786 posts · Server pawoo.net アタシのパートナーとしてね、と心の中で付け加える。いまこのセリフをぶつけるには早い。そんなことを言えばジャックは無理をするに違いない。成長してくれるのは嬉しいが、無理に背伸びすればひょろひょろになってしまう。
「うっす! ヴィル先輩を堂々と誘えるように努力します」
「誘う?」
「あー……どっか出かけようって、遊びにです」
「アンタが遊びに? ふーん? 遊びにねえ……」
ヴィルはくつくつと笑った。
「いつでも誘いなさい。子どもの時みたいに」
そう言うとジャックの尻尾がボンと膨らんだ。ヴィルはいい気持ちで階段を降りると、胸を張ってジャックの腕に手を絡め、「いかにも捻挫で後輩に手助けしてもらってます」を粧ってつかの間のパートナー気分を楽しんだのだった。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
7 followers · 786 posts · Server pawoo.net ギリギリとジャックが歯ぎしりする。キャッチ・ザ・テイルでヴィルが捻挫させられたこともだし、そのことに気づかなかったこともジャックを苛立たせているようだった。
「アンタは調子はどうなの?」
「もう全然元気っす。朝もランニングしてきました。ひとりで走ってたんですが、ヴィル先輩がいるほうが気合いが入ります」
「アタシがいなくても気合い入れなさい」
「まあ、そうっすけど……張り合いがないっす」
「アンタ、張り合いなんてなくてもやるじゃない」
一人でがむしゃらに、と付け加えるとジャックは頬をぽりぽりと掻いた。
「……迷惑じゃないっすか?」
「なんでよ?」
「ラギー先輩は嫌がったんで」
「ま、ラギーはそうでしょうね。無償の奉仕ぐらい高くつくものはないって知ってるんでしょ」
そしてヴィルも知っている。入学時には有象無象がまとわりついてきて鬱陶しいこと限りなかった。でもジャックだけはこうやってまとわりつかれても疎ましくない。できればもっと一緒にいてほしい、とさえ願ってしまう。願うなんて自分らしくない。
「ま、精進なさい」
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
7 followers · 786 posts · Server pawoo.net【パートナーとして・ジャクヴィル】
タマーシュ・ムイナ。
色んなことがあったイベントだった……と思いつつヴィルは湿布を貼り直した足を庇いつつ立ち上がる。松葉杖がいるほどではないが、未だに痛む。肩にかけたカバンが重い。魔法で浮かして持っていこうかとも思ったが、これくらいのサイズのものを浮かし続けるのは難しい。
「ヴィル先輩! おはようございます!」
自室のドアを開けるなりジャックがいて思わず後ずさる。何でアンタがいるのよ、というセリフが引っ込んだのは、ジャックの後ろに朗らかな笑顔のルークが手を振っていたからだ。
「おはよう、待ってたの?」
「うっす。カバンを持ちます」
「結構、と言いたいところだけど助かる。重たくて」
それでも寮生に頼もうと思わなかったのは、寮生は自分の下僕ではないからだ。あくまでも美しく育て上げるべきイモ。かと言ってルークに頼むのも癪に障る。人に頼るのが下手、と言われたらそれまでだが……、こうやって自ら協力を申し出てくれるなら話は別だ。
「ありがと、ジャック」
「とんでもない。俺が選手だったら、あんな奴一瞬でしめてやったのに」
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
7 followers · 786 posts · Server pawoo.netきっとジャクヴィルの関係に変化があったに違いない!いやないわけがない!
タマムイはジャクヴィルの関係にニトロをぶち込んだサイコーのイベントでしたね……
捻挫してしばらくランニングが出来ない代わりに、毎朝ジャックくんがヴィル様をお迎えに行きます!
薄明かりに浮かぶ恋/誓いのストロー・ジャクヴィル | たまりすい(溜すい) #pixiv https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19382696 #ジャクヴィル
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
5 followers · 231 posts · Server pawoo.net「そうっすか……」
といいつつジャックは出されたフルーツを見つめた。夕焼けの草原国で見たジャックフルーツを、まさかヴィルの自室で見ることになるとは思わなかった。美味いことは美味いが……微妙な気持ちになる。
「なんで疑問形なのよ」
「違いますって相づちです!」とジャックは顔の前で手を振った。「ヴィル先輩はいつもキレイっすから……あ、可愛くみえるときもあるっすけど」
「はい、あーん」ヴィルがフォークでジャックフルーツを刺し、口元に差し出してくる。「ほら、あーんよ。あーん。ヴィラでも食べたでしょ、こうやって」
「はい!?」
尻尾をぼんっと膨らませてジャックが声を上げれば、
「アタシばっかり可愛いはズルいでしょ。アンタも可愛い顔を見せてちょうだい」
そうしたらもっと綺麗になるから、アタシ、とにっこり笑われては食べるしかない。ジャックは照れくさいような、恥ずかしいような、なんとも説明のできない甘い気持ちを味わいつつ、足の裏をもぞもぞとさせながらヴィルの手からジャックフルーツを食べたのだった。
たまりすい(溜すい) · @tmrsi
5 followers · 231 posts · Server pawoo.net【恋のコスメティックス】 #ジャクヴィル
ヴィルに呼ばれてポムフィオーレ寮にやってきたが……、なんだか、入るなりじろじろと見られているような気がする。
というか、
「ジャックが全然手に入らない……」「ジャック予約できた?」「ジャックの効能凄いぞ!」
と、何じゃそりゃ?、の会話が繰り広げられている。しかも普段ならばポムフィオーレ寮生に敵愾心を向けられ、決闘を申し込まれることもままある。が、今日は好奇……いや、ギラギラとした目で見つめてくる。あまり物怖じしないジャックだが、今日ばかりは薄気味悪く感じ、急ぎ足でヴィルの部屋に向かった。そして勧められたソファに座るなりジャックは訊ねた。
「ヴィル先輩、寮内で俺の名前が連呼されている気がするんですが」
自意識過剰よ、とヴィルに一言の元切って捨てられる、と思いきや……
「あぁ、流行ってるの、うちの寮でジャックフルーツ」
「はぁ!?」
「アタシが夕焼けの草原国から帰ってきてから、また美貌に磨きがかかったと評判なのよ」
温泉パワーかしらね、とヴィルは目を細める。