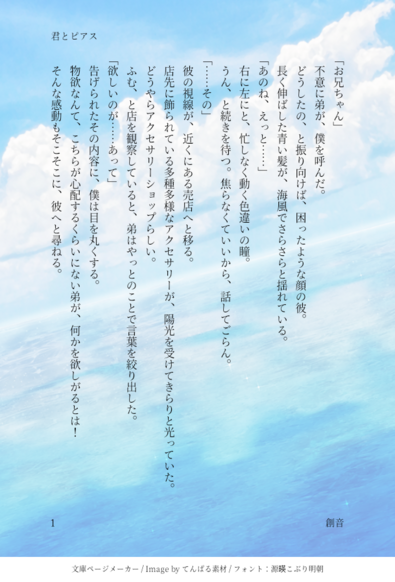羽ペン · @goodquillpen
59 followers · 826 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
○○の言葉、クリスマス、昼と夜の物語、幸福をもたらすもの
(だいぶニュアンス含む)
クリスマスが自分のための日ではないということに思い至ってから、私はこの日を気にかけることをやめた。若いころはそれでも周囲の環境や知り合いたちの言葉などに思い煩うことも多かったが、幸いにしてここ数年は会社の新規事業が軌道に乗り、その流れで新しく始まったプロジェクトのチームに選ばれ、昨年からはリーダーを務めていることもあって、忙しない年の瀬を過ごしている。
それでも家庭があるものや何かしらの約束事を取り付けているメンバーはどうにかして十二月二十四日の夜は残業せずに帰ることに努め、“そういった”ことに自分の時間を割く必要のない私は喜んで彼らの仕事を肩代わりした。
「喬リーダー、ありがとうございます」
「明日お昼奢りますんで!」
「はいはい、ありがとうね。早くお帰り」
さっさと手を振ってやると、私よりも若いメンバーたちはうきうきと軽いステップでオフィスを出て行った。彼彼女らを見送り一人残されたオフィスで、この寒い季節に元気なことだと嘆息する。それでもきっと、“心はあたたか”なのだろう、とも。
そう、若いころは、きっとああしたことが幸福の源泉なのだろうと思っていた。そして、それらは常に私には縁のないことなのだと。親兄弟とは決して疎遠なわけではない。だが一人、都会に出てきて働きながら年を取り、いつしか誕生日を祝わなくなるのと同じように、クリスマスだって自分自身からは縁遠いものに変わった。子供のいる弟一家や妹一家は恐らくそうではないだろう――しかし若いころと違って甥っ子や姪っ子のためのクリスマスプレゼントを購入する機会もなくなった――が、それすらうらやむことも今ではない。
私がキーボードをたたく音だけが響く静かなオフィスに、どこかで鳴っているのであろう賑やかなクリスマス音楽が微かに聞こえてくる。窓の向こうに目を遣れば、街中できらめいているのであろう色彩豊かなイルミネーションの存在がここからでも感じられる。
誰かが喜ぶのであればすべきなのだろう。私は本当に、ああしたことに動く心を持っていなかった。
――そんなんで人生つまらなくない?
かつて、同僚にそんなことを言われたことが思い出される。どういった文脈だったのかは覚えていない。ただ、どうしてそんなことが、私の人生が面白いか、つまらないかの評価につながるのかがわからなかった。思い煩ったのはそのことだった。どうやら、世間は私が思うようには動いていないらしいのだ。
一時間ほど作業をして、ちょうどきりのいいところまで終わった仕事に満足する。さて明日は何を奢ってもらおうかと考えながらPCを閉じ、私は立ち上がった。
帰社前の最終確認を行うためにオフィスを歩いていると、共用の低いファイルラックの天板に置かれてある、モミの木と小さな家を模したオブジェが内部に収められているスノードームが目に入った。どうやらライトも内蔵されているようで、持ち主か誰かが消し忘れてそのままにしていったらしくぴかぴかとひかめいている。
私はその傍に近寄るとスノードームを持ち上げた。小さな家の脇には雪だるまがいて、私がひっくり返すと舞うイミテーションの雪のなかで笑っている。
窓の脇に立ってスノードームを思いきり振った私は、それをイルミネーションの影にかざした。
白、ピンク、水色、茶色、黒、赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫――
その光は私の瞳に映り、揺れている。
スノードームを見つめていた視線を上げると、空に月が輝いていた。
翌日、私はプロジェクトメンバーたちにタイ料理を奢ってもらうことにした。先々月にオフィス近くのビルに新しく入ったタイ料理店にずっと行ってみたかったのだと言うと、皆して口々に同意してくれ、何人かは実はもう行ったことがあると答えた。
「タイラーメン、美味しそうだと思って」
「おいしかったですよ! おすすめです」
「私はパッタイにしようかなあ」
「パッタイもいいよ! おすすめ」
「ねえ、揚げ春巻きも頼みません?」
「揚げ春巻きもめっちゃおいしいよー!」
何にでも乗り気で口を挟んでくるメンバーの一人に私たちは笑いながら、それぞれ自身の食べたいと思ったものを注文する。私は最初の予定通りタイラーメンを注文して、併せてメニューの隅に載っていたタイミルクティーをアイスで追加注文した。この時期にアイスかとメンバーの一人に驚かれたが、私は「ラーメンを食べたら熱くなるかと」と返す。
そうこうしているうちに先に届いたのはタイミルクティーだった。金色に塗られたアルミ製のティーカップは口が広く、高さはそこまで高くなく作られていて、高台のない椀のような形状にきめ細やかな模様が彫られている。
「わ、冷た」
カップに触れると思ったより冷えていて私は思わず声を上げた。
「アルミです? 熱伝導率高いのかもですね」
「そうだねえ……」
両手の人差し指と親指で注意深く挟みながら、一口、一口と飲み進める。ほうじ茶にバニラを混ぜたような味わいと書かれてあったが、私の口ではどうにもココアに近い飲み物に思えた。いずれにせよ美味いことには変わりなく、アイスではあったもののゴクゴクと飲んでしまう。
そのうち、表面が下がってくると大きめの氷がカップの底について、底の金色を透過してきらめいているのが見えた。
「……喬リーダー? 何見てるんです?」
ずいぶんしばらくそれを眺めてしまい、メンバーたちに訝られていることに気づく。私がティーカップを差し出して氷について述べると、皆も順番に覗き込んでは「きれい」「いいですねえ」と楽しげに笑った。
ほどなく私の手許に戻ってきたティーカップを再び覗き込み――私は、昨日のスノードームとそれに反射するイルミネーションの極彩色を思い出す。
「リーダー、めっちゃ嬉しそう」
「え?」
「素敵ですよね」
一人の言葉に、私は小さくうなずいた。
タイミルクティーの茶色、透明な氷、影の青や黒や紫、底で揺れている金色……。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
55 followers · 661 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
不変の○○、おねがい、半袖
俺の友人、小矢部は、持っているTシャツの種類がやたら多い。どこで売っているのかわからないようなセンスのデザインが多く、有名人で言うとイチローの着ているTシャツのセンスが親しみやすさの表象としてネタにされて久しいが、小矢部自身は彼に憧れているわけではないらしい。というか、野球に興味もなければ家にテレビもないのでイチローのそういう姿を見る機会がない。ネットでも出会わなかったなんて奇跡じゃないか? って俺はちょっと思っている。
今日は胸許にでかでかと「STOP!増税」と書かれた白いTシャツだった。マゼンタの地色に黒で表記されるそのメッセージは目を引く。
「売ってんの? それ」
「売ってる。SUZURIで買った」
「すずり?」
「知らんのか。グッズ販売ができるサービスがあるんだよ」
「ぶーすじゃなくて?」
「BOOTHとはまた違う」
「ふーん……?」
俺は俺でいまいち小矢部の言うことに理解が追いつかないところが多々あった。いわゆる同人? というものらしいが、俺の人生で通ってこなかった世界である。
「んでも、増税反対は賛成だなー」
「そうだろう」
俺の隣を歩く小矢部は背筋を伸ばし、シャキシャキと歩く。俺たちは高校一年のときからの友人同士だが、小矢部は昔からこうで、俺と出会う前からもずっとこうだったんだろうと思う。俺も小矢部も友人を作るのがいまいちうまくできなくて、学校行事のたびに自然と二人で組まされているうちに本当に仲良くなったというのが経緯だ。
今日は気温が三五度を超える予報が出ていて、さわやかな増税反対Tシャツの半袖から伸びる小矢部の腕がよく焼けているのが見える。俺は日焼けをすると赤く腫れてしまうたちだったから今日も日焼け止めをしたうえに長袖のカーディガンを羽織ってきた。健康的に焼けることのできる小矢部のことを夏が来るたびにうらやましく思っているのは、常から小矢部に伝えていることだ。
「志野、カード」
「あ、うん」
ショッピングモールに併設されている映画館は、ちょうど昼時なこともあってやや閑散としている。
小矢部は映画というと「昔『十二人の怒れる男』を観たきりだ」なんて言うくらい縁がないみたいだったけど、俺があるとき、ホラーが苦手なくせに話題になっているからとどうしても観たかったホラー映画を、一緒に観よう、おねがい、と何度も――それでもなるべく嫌がられないテンションを心掛けて――頼んだら、別にいいよ、と返してくれた。
「そんな必死にならなくても、最初から、嫌だなんて言わない」
事も無げに小矢部がそう言うので俺は心からほっとしてしまった。
もしかしたらあまり理解してもらえないかもしれないけれど、自分が何が好きか、と誰かに伝えることが俺はすごく苦手だった。というか、苦手意識を感じていた。ましてやそのときはホラー映画だったから、苦手なくせに観るなんておかしい、と言われることすら覚悟していたのに、小矢部は一言もそんなことを言わなかった。
「なんで話題になったかわかるし、お前が観たかった理由もなんとなくわかった」
小矢部はそう言って、「また誘ってくれ」と続けた。俺が泣きそうになったその日も夏で、小矢部は胸許に達筆で「地球温暖化」という文字と真っ赤になった地球が描かれたTシャツを着ていた。
今日観る映画は中国で作られた歴史アクション映画だ。1は日本に来なかったのにどういうわけか2が来た。そう言うと小矢部は、「そういうことあるよな」と口にした。
「でも、1が来てないから俺たちは今のところこの映画二人占めだ」
買ったチケットを小矢部に渡すと彼はニヤリと笑う。俺もうなずいた。俺たちが映画を観に行くとこういうことが結構あって、広い客席の本当のど真ん中を陣取って観賞する二時間はなんだか特別な気分で楽しい。
「もしかしたらさ」
場内が暗くなる前の五分間、ぼんやりと予告編が流れるスクリーンを見ながら小矢部がふと口を開いた。
「ん?」
「チケット、高くなったろ。値上げも少しは影響しているかもしれない」
「ああ、人がいないの」
小矢部に言われて、そうかもなあ、と俺はうなずいた。二〇〇〇円近くは、さすがにきついよな。
「でも、本当に観たい映画ならあまり気にしないことにしよう。俺は平気だから」
「あ、うん……」
俺が横にいる小矢部を観ると、小矢部はスクリーンを見たまま、
「推し活だろ」
と言った。
「推し活」
「そう。推し活。俺のTシャツと同じ」
「あ、それ推し活なの」
少しばかりびっくりした俺が早口で返すと、小矢部はうなずく。
「増税反対を推してる。増税反対……とか」
「とか? 他には?」
俺が訊くと、そこで小矢部はやっと俺を見た。なんでか、向こうも驚いた様子だったので俺は首をかしげてしまう。
「……差別反対とか」
「あ、それ。不変の誓いだな。そういうのも推せるのか」
「……あと、柴犬命」
「急に」
おかしくなって俺は笑った。小矢部も笑っているうちに場内が暗くなって、俺たちは自然と居住まいを正してスクリーンに向き直る。
映画が終わったら、今、小矢部が着ている「STOP!増税」のTシャツを、俺も買えないか訊いてみよう。すずり? もよくわかんないけど、訊いたらきっと教えてくれるだろう。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
終わり方中途半端😭
羽ペン · @goodquillpen
51 followers · 525 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
おそろい、どこか遠くへ、贈り物、きらきら光るお空の星よ
イドリスが一度故郷へ戻ると言って出て行ってから十年が経つ。イドリスの故郷はこの星からは何億光年も離れているらしいけれど、この星の恒星間移動技術があれば片道何億光年の距離だろうと思っているほどは時間はかからない。それでも、行きに三年はかかってしまうのだけど。
イドリスからは毎日のようにメッセージが届いた。ビデオメッセージのときもあればボイスメッセージのときも、テキストメッセージだけのときもある。私は彼女の気さくな文章が大好きだったから、テキストだけでも寂しくはなかった。でも次第にその頻度は少なくなり、イドリスと離れて六年目を過ぎるころには、ひと月に一回届けばいいほうになっていて、今はもう三月届いていない。
彼女の出発の直前、私とイドリスはお揃いのマスカレンタイトのリングを作り、お互いへの贈り物にした。リングと言っても、私のそれは指にはめるもので、彼女のそれは手首にはめるものだ。そこまでちゃんとはお揃いにできなかった。マスカレンタイトには「離れてもそばにいる」という意味がある。イドリスが彼女の言葉で、「ファレナが私のそばにずっといますように」と祈ってくれて、そしてキスをしてくれた。イドリスのやわらかな頬の毛並み、私に添えられた肉球の優しい冷ややかさ、鼻先の湿り気は片時も忘れることがない。
イドリスが故郷に戻った理由は実家の整理だ。イドリスの故郷はすっかり荒廃してしまって、棲んでいた生き物のほとんどは絶滅するか、故郷の外に新しい安住の地を求めたらしい。イドリスの一族もそうしてばらばらの道を辿り、イドリスだけが私の星に流れ着いた。
どれほど時間が経っても故郷は忘れられない。遺してきたものの形がすっかり失われてしまっても。
彼女は時折そう口にした。そのたび私は共感するふりをして、そんなものどうだっていいのに、と思っていた。
私とイドリスが一緒にいること以上に大切なものなんてこの宇宙にあるんだろうか?
十年離れて、そのことを考えない日はない。私も一緒についていけたらよかったのに、私はこの星から出ることができない。イドリスのように自由に外に出られる体ではないのだ。
私たちはこの星で一緒に過ごしながら、いつかどこか遠くへ遊びに行こうね、と口約束を交わし合った。私のそれは叶うことのない夢物語で、イドリスにとっては私に見せてやりたい風景のひとつだった。イドリスは、彼女の辿ってきた道をたくさん私に語って聞かせてくれ、私は彼女の言葉で宇宙の果てまで旅をした。
この宇宙は穴ぼこだらけ。行く当てのない生命がそこらじゅうに吹き溜まり、その虚ろを新しい家にする。誰にも知られず生きていられる、そのことに安堵しながら。
イドリスの故郷が荒廃した理由を、イドリスは「わからない」と言った。様々な要因がある、と。すべてが交差し、絡み合い、相互に作用して、滅びに収束したのだ、と。
「私もそのときになるまで大した勉強をしなかった」
イドリスはまるで懺悔するようにそう言った。その姿がかわいそうで私が抱きしめると、彼女は私の肩口にやわらかな顎をそっと置いて、小さな声で「ありがとう」と言ってくれた。
私はイドリスに、ずっと私の腕のなかにいてほしかった。
イドリスのなかには、ずっと故郷の風景があった。
イドリスと離れて十年と一日目。星空を見上げても、光の粒のなかに彼女の乗った宇宙船の姿はまだ見えない。
私は毎日起き抜けに、彼女の教えてくれた故郷の歌を口ずさむ。
「きらきら光る、お空の星よ……」
私は悔しさに歯噛みする。光っているだけで何もしてくれない星の歌を、ただ見ているだけの星の歌を、どうしてイドリスはあんなに恋焦がれるような歌声で歌ったの。
イドリスが帰ってこないのは、私が心の世界で彼女の故郷の荒廃を喜んでしまったから? そのことが見透かされてしまったから? だって、彼女の故郷がなくならければ私は彼女に会えなかったのだから。
食いしばった歯の向こうから恐ろしい呻き声が聞こえる。こんな音、彼女には聞かせられない。
あんなに故郷のことを愛していたイドリス。一度戻ってしまったら、二度と私の許へ帰ってくることはないかもしれないと、私は心のどこかで疑っていた。本当にぎりぎりまで、私は彼女を縛りつけて、戻るなんて言わないで、と縋りつくことすら考えていた。それでも、出発の前日の夜、彼女が私にくれたキスが、そうさせてはくれなかった。
あんなに嬉しそうに、すぐに戻るよ、と宇宙船に乗り込んだイドリス。
あなたが喜ぶことなら、私は止められないの。
「この曲にはね」
イドリスは、私の頬を優しく撫ぜながら、詩を紡ぐように美しい声でささやいた。
「たくさんの歌詞がつけられていて、今私が歌ったのは、私の故郷で一番有名だったものだよ」
「そうなんだ、素敵な歌だね」
「うん。ふふ……だからね、ときどき、私も自分で作った歌詞を音楽に載せたりしていたんだ」
「本当? 聞かせて」
すり寄って乞う私に、イドリスは恥ずかしそうに目線をあちらこちらに遣りながら、首を振った。イドリスのすべてを知りたがっている私がごねると、彼女ははにかんで、「じゃあ、いつかね」と、「約束するよ」と言ってくれた。
あなたは言ってくれたの、イドリス。
ビデオメッセージもボイスメッセージも、テキストメッセージももう要らないの。あなたが私の許に帰ってきてくれないなら、全部無意味なの。
私は、彼女が私にくれるすべてが約束だと思っていた。
私の指に光るマスカレンタイトが湿っていく。私の口が発する呻き声は地鳴りのようで、雷のようで、イドリス、きっとあなたには見合わないかもしれない。こんな恐ろしいものは本当はあなたに聞かせたくない。
それでも、イドリス、あなたが恋焦がれるように歌ってくれた、あなたの故郷の歌にあるように、星がきらめいているなら。
お願い、私の夢も届けて。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
48 followers · 439 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
○○に染まる、怒り、バイキング
怒りで目の前が真っ赤に染まる、という慣用表現は思いのほか正しいのかもしれない。真っ赤とはいかないまでも、やけに赤みがかって見えたものだ。あいつの頬の色も。
「俺、やけ食いする人間初めて見たよ」
プレートにシーザーサラダとハンバーグとキッシュをそれぞれ控えめによそい、目の前に坐った浜畑はため息交じりに言う。呆れたような態度が癪に障る。
「昔からこうやって怒りを鎮めてきたんだ」
「昔から?」
俺の言に浜畑はまたしても素っ頓狂な声を上げた。
「なあ、それはさ、うーん、あいつの心配もわかるよ俺は」
肩を落とし、浜畑はシーザーサラダのレタスを食べる。俺はローストビーフを山のうえからもう一切れ箸でつまんで口に運んだ。
――正直な話、俺の怒りはもうとっくに鎮まっていた。バイキングの料金を浜畑の分も一緒に払っているときから、本当はもう、引っ込みがつかなくなっていただけなのだ。奢り前提で愚痴を聞くよと調子のいいことをのたまった浜畑には、頼むから料金分の料理をたらふく食ってほしいものだ。
『なあ多紀、こないだの健診の結果、俺にも見してよ』
毎年の健康診断のメニューに胃カメラが追加されるようになってから、あいつは俺の診断結果を確認したがるようになり、明らかにその内容に一喜一憂することが増えた。一度、日常の話のタネにと「そういやこないだの健診で血圧が少し高めって言われてさあ」なんて口にしてからだったと思う。
あいつは、あいつの家族とは結局わかり合えないまま俺と一緒にこの街で暮らし始めたし、それ以来一度も自分の家族には会っていない。けれども、あるとき苦しそうに「父さんは昔、狭心症から心筋梗塞になって倒れたんだ、なんとか助かったけど」と打ち明けてくれたことがある。そう、一度だけ会ったことのあるあいつの父親も、俺と大体似たような体格をしていた。
「お前らずっと一緒に生きてくんだろ、こんな田舎で」
「…………」
「じゃあ、やっぱ、ゆずり合ったほうがいいよ。少しくらいはさあ」
そうしてポテトサラダを口に運ぶ浜畑の物言いに、俺は言葉を返せなかった――ずっと、返す言葉なんて見つからなかったけど。
あいつが“俺のため”を思って言ってくれたことだと頭ではわかっている。浜畑もその立場だろう。だけども俺は食うことが好きだ。自分でもそうだし、あいつが目の前で飯でもお菓子でも、何かをうまそうに食っているのを見るのも好きだ。飯を食いながら言葉を交わすのが好きだったし、俺があいつに惚れて――あいつは自分が俺に惚れたんだって言うけど――付き合うようになったのだって、そのへんのことが理由だった。
『なあちょっとずつさ、体にいいもの食べようよ。好きなものだけじゃなくてさ』
なんでこんなに簡単に、頭に血が上ったんだろう。
箸が止まってしまう。浜畑も無言でいる。賑やかなバイキングレストランの店内で唯一つまらない空間になってしまった俺たちの周囲で、携帯の着信音が軽やかになった。
「お前じゃね? 出れば?」
「…………」
あいつと俺とは、飯食ってるときには絶対携帯を見ない、ってところも気が合った。
頓着しない浜畑の言葉を受けて俺が鞄から携帯を取り出すと、ロック画面にあいつから来たメッセージが通知されていた。
[ごめん]
立て続けに、ぽこん、ぽこん、とメッセージが届く。バナー通知の画面だから、全部は読めない。
[多紀のことないがしろにした。俺の気……]
[体にいいものを、多紀の好きな味で食……]
[一緒にチャレンジしてみない?]
…………。
「……返信してもいいか?」
「好きにしろよ。俺はおかわり行ってきまーす」
いつの間にかプレートを空にしていた浜畑は立ち上がり、料理の並んだスペースに歩いていく。俺は箸を置いて急いでメッセージに既読をつけた。
[俺こそごめん。柊弥が俺のこと心配してくれてるのはずっとわかってた]
[意固地になってた。本当にごめん]
[ほんで今浜畑にやけ食いに付き合ってもらってるから、返事は帰ったらする。でも、しゅうの話に全面的に賛成します]
[本当にありがとう]
送り終えて、もう少し何か付け足そうかと悩んだところですぐにあいつから返信が来た。
[もー!たくさん食べておいで!帰ったら俺と一緒にプリンね!]
「…………」
ガタリ、と対面の椅子が引かれて、新しいプレートに新しい料理群をしこたま載せた浜畑が戻ってきた。
「何ニヤけてんの」
「うっせ」
「それよりチョコフォンデュあるの知ってた?」
「知ってたけど、今日はやめとく」
浜畑は俺を半眼で睨みつけ、それから盛大にため息をついた。なんだか申し訳ない気もしたが、やつのプレートに載っている量ならもしかしたらそこそこ元は取れそうにも見えたので、それで勘弁してほしい。
「なんかごめんな」
「いーよ。お前の奢りだし、珍しかったしな」
このうえ俺のプレートに作られたローストビーフの山から一切れをフォークで刺して持っていく浜畑は、どこか嬉しそうに見えた。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
45 followers · 289 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
平凡、お互いを見つめる
人物紹介の一行目に「どこにでもいる平凡な○○」と書かれる主人公が嫌いだった。そいつは主人公なので必ず何かを成し遂げる未来が確約されている。こういう主人公が登場する物語には、バトルをテーマにした作品であろうとスポーツをテーマにした作品であろうと、その他であろうと、たいてい主人公の仲間がいて、ライバルがいて、ライバルどころではない圧倒的な敵がいて、その他大勢のいわゆるモブがいる。当然、「どこにでもいる平凡な」と書かれる主人公に「負ける」キャラクターも出てくる。
「どこにでもいる平凡な」主人公に共通する性質を私は知っている。それは、「たゆまぬ努力を積み重ねる」というものだ。この性質により「どこにでもいる平凡な」主人公は「そうではない」何者かになり、最終的には何かしらの成功を収める。
真昼間のファミレスで私のこんな愚痴を嫌な顔ひとつせず聞いてくれるのは、会社の新入社員歓迎会をきっかけに仲良くなった総務部の水谷さんだ。水谷さんは、私が歓迎会の席で隣になった同じ部署の先輩としていた会話を耳にしたことで後日「すみません、もしかしてシッパーですか?」と遠慮がちに訊いてきたという猛者で、私はというと当然大いに動揺し、「私もなんです」という彼女の笑顔がなければ最悪そのまま逃げ去っていたかもしれない小心者である。
逃げなくてよかった。なにせジャンルは違うが話が合う。我々の界隈ではよく「ジャンルの切れ目が縁の切れ目」などという格言が取り上げられるが、そもそもジャンルが違う状態で知り合っている我々なので、今のところ変なぶつかり方――察してほしい――をせずに済んでいる。
水谷さんは様々なジャンルの知識を広く持っていたが、特に熱心に活動しているのは小説二次だそうだ。基本的に漫画ジャンルのオタクだった私にはまったく覚えのない分野ではあるが、その後おすすめしてもらって読んだ京極夏彦の『巷説百物語』シリーズはとても面白く、実はあまり大きな声では言えない妄想もしてしまった。一部の人にはときどきあることだと思いたい、「別に読まないし、書かないけど、この人は“こっち”だな」という目でキャラクターを見ることは。
「努力できるのって才能みたいなとこ、実際あるよね」
「そう! そういうこと! どこにでもいる平凡なとか、言わないでほしいの」
水谷さんの相槌にここぞとばかりに私は乗る。
「努力家ですって胸張って言ってほしいの」
その昔、私の好きな漫画に出てくる私の好きなキャラクターは「どこにでもいる平凡な」主人公に敗北を喫した。いかにも何かありそうな感じで物語中盤で登場し、“現実だったら”絶対こっちのほうが勝つだろみたいなところで、主人公の主人公パワーによりあえなく負けた。以降、ネームドではあるがその他大勢のひとりのような扱いで物語の端々に登場するだけの存在になってしまい、大した台詞もなく、いつしか物語の本流からいなくなった。
私にはそれがとてもつらかった。
「別に勝ってほしかったわけじゃないの。漫画のなかで、もう、その他大勢になっちゃったのが……」
「見えなくされるの、つらいよねー」
水谷さんが言う。私が、いつの間にか空になったグラタンの皿を見つめるだけになっていた顔を上げると、水谷さんも私を見ていて、お互いに見つめ合ってしまった。
「……小説ってそういうしんどさとか書いてるの、いっぱいありそう」
「ええ? 漫画も結構あるじゃん。あるよね?」
「多分あるけど……ここだけの話、オタクがTwitterで変な盛り上がり方してるやつには近寄らないようにしてるから」
「あはは!」
正直、水谷さんにしか言えないぶっちゃけ話を初めてすると、思った通り水谷さんは笑ってくれて、私はそのことにすごくほっとする。
「あ、ねえ、じゃあさ、今度一緒に映画観に行かない?」
水谷さんに切り出されて私は瞬く。知り合ってから初めての映画鑑賞のお誘いだった。水谷さんは携帯をいじくって開いた画面を私に見せる。
「この映画、そういう感じのしんどいやつなんだって。一緒に傷つきに行こうよ」
「えええ……そんなの自分から観るの……?」
「試しに一回。だってこんな話できるの香坂さんだけだもん」
お願い、と顔を覗き込まれるように小首をかしげられ、私は思わずうなずいてしまった。「嬉しい、ありがとう」と本当に喜ばしそうな水谷さんとなら、一緒に傷ついてももしかしたらちょっとくらい平気かもしれない、と思える。
「香坂さん」
「ん?」
ドリンクバーに行って戻ってきた水谷さんが、向かいの席に坐り直しながら私を見て、言う。
「今度、私の書いた小説読んでほしい」
「……!! ぜひ!!」
いずれにしても、私は、水谷さんともっと仲良くなりたいのである。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
:penny_farthing: · @maitaimemory
19 followers · 179 posts · Server social.vivaldi.net砂波は蠢めく人影を止めることがどうしてもできなかった。近寄ってみることさえも。足全体をそこに固めるなにかがあるかのようだ。
足は動かない。だがしかし腰から上は動かせた。蠢めく人影は止められない。しかし腰から上を旋回させることならできた。
砂波は懸命に腰から上を旋回した。回れまわれ、わたしの上半身。
やがて蠢めいていた人影はピタリと止まる。糸がピンと張ったような沈黙だ。
あれはなんだ。
回れ、人の目を忘れて、恥じらいを捨てて。回れわたしの上半身。
「深淵を覗く」
創音(きずね) · @kizune
25 followers · 571 posts · Server otadon.com
羽ペン · @goodquillpen
40 followers · 47 posts · Server pinnipedia.fedicity.net【使ったお題】
ほんのちょっとの○○、きのこ、お兄ちゃん
兄である福士(ふくし)の機嫌がいいと幸子(さちこ)も嬉しい。
二人の父親である恵(めぐむ)が一年前に土砂崩れに巻き込まれて他界してから、遺された母親の頼子(よりこ)を支えるために福士は自身の勉学のための時間を削ってまでバイトに勤しみ、家計を助ける生活を送り続けていた。
幸子はまだ中学生で、何より最高学年であり、高校受験が控えている。「高校進学しないで私も働く」と主張した幸子を、頼子と福士は二人して泣きながら「お願いだから進学をしてくれ」と声をそろえて縋るように訴えた。頼子などは、「恵くんはあなたの学費の分も遺してくれているんだから」と続けた。幸子は、その場はいったん頷かずに置いておき――
なぜか幸子にだけ見える、幽霊の恵に問いかけた。
「それは本当なの」
と。
恵はにこにこ嬉しそうに頷いた。
『本当だよお、さっちゃん』
と。
なぜ幽霊の恵が幸子にだけ見えるのかはわからない。恵も、頼子と福士には自分が見えないことを不意に寂しそうに感じている様子も見られた。それでも、『さっちゃんに見えるならぼくはそれで嬉しいよ』とやはり嬉しそうに笑うのだった。
幸子自身は、恵が自分の前だけに現れるのは、何か自分に恵に対する後悔があるからなのではないか、と踏んでいる。何せ恵が死んだとき、幸子は反抗期真っただ中だった。いつもヘラヘラ笑っている父親がどうしても嫌いに思えて、一日じゅう口を聞かずにいることもあった。そのころ高校一年生だった福士はときおり幸子を咎めたが――なんとこの兄には反抗期というものがなかったようなのである――、頼子は困ったように笑って「そうだねえ、恵くんちょっと過干渉」と幸子の味方になってくれた。
その感情がいつしか凪いでいき、あとほんのちょっとの意地さえどうにかなれば、父親と何か一言二言会話ができるかもしれない。恵が事故に遭ったのはそんなときだった。
『本当はふーくんにも、自分のために勉強してほしいんだけど』
「お兄ちゃん、頑固だから」
『ね。誰に似たんだろうね……』
幸子と恵の会話は主に登下校時や、頼子がパートから、福士がバイトから帰ってくるまでの、幸子の留守番している時間帯に行われる。家では、幸子の部屋に入ることを恵は正しく遠慮し、そして二人の前ではこうした会話は不自然に思われたから、いつしかそのような習慣がついていた。
頼子も恵も、そこまで剛情な性質を備えているわけではない。むしろ福士は両親がそうした性質であったからこそ、態度や語調の物柔らかさに反して狷介な気質を育てていったのかもしれない。ちなみに幸子は面倒くさがりで自分に甘く、これは多分に両親の性質と似ていた。
恵はひしゃげた眼鏡のブリッジをくいと上げて、ため息をつく。
『ぼくにもっと甲斐性があればなあ』
「甲斐性で土砂崩れを防げたら世話ないね」
『おっしゃる通りで』
校門まで着くと、恵はそこで手を振っていったん幸子の前から消える。四六時中自分がついていると幸子に申し訳がないからと、ずっと校門のところで待っているのだそうだ。“取り憑いている”わけではないんだなあ、と幸子はしみじみ思う。そうして、幸子の学校生活が始まる。幸子はいつも思っている。そうやって自分の目の前から消えている間に、本当に恵はもう一度いなくなってしまうのではないか。二度と現れなくなってしまうのではないか。
自分は父親をもう一度喪ってしまうのではないか。もしかしたら、それが自分への罰なのではないか。
部屋の扉がノックされて、勉強のために机に向かっていた幸子は返事をした。遠慮がちに開いた扉から顔を見せたのは兄である福士で、「どうしたの」と訊ねる幸子に珍しく彼は彼らしくなく何度も言い淀んで、ついに「明日、バイトなくて、友達を連れて来たいんだ」と口にした。
「え? うん。それが?」
「さっちゃんもご飯食べるだろ?」
「え、食べるよ……何、だめなの?」
「いや、そうじゃなくて。友達、も一緒に……」
「ああ」
幸子は頷いた。
「うん。別に。あたしはいいよ。何? 明日お兄ちゃん作る?」
「あ……うん。それいいな。そうしようかな」
どこかほっとしたように微笑んで、こくこくと首肯する福士に幸子は違和感を覚える。どうにも妙に煮え切らない態度だ。
「母さんにはもうオッケーもらってて……ただ、母さん明日遅番だから」
「じゃあ、三人ってことか。うん、いいよ。最近ずっとあたしばっかり作ってたし、お兄ちゃんのご飯楽しみにしてる」
福士は再び頷くと、夜のあいさつを残して部屋を辞去した。机に向き直った幸子であるが、兄の様子が解せなくて首をひねる。そこでふと、幸子は恵のことを思い出した。
(お父さん、ちょっとあたしの部屋に来て)
幽霊の恵が見えるようになったころから、彼に向かって強く念じればテレパシーのようなものが使えるようになっていた幸子は久しぶりにこの能力を活用する。じきに部屋の外から遠慮がちな入室の許可をもらう声が聞こえて、幸子は今度「どうぞ」と声で返事をした。恵は扉をすり抜けて現れた。
「明日、お兄ちゃんの友達も一緒に晩ご飯食べるって。聞いてた?」
『聞いてなかった。盗み聞きになっちゃうし……』
「なんか、そういうとこ変にしっかりしてるよね。あたしだったら好き放題聞いちゃうな」
『えへへへ』
褒められちゃった、と頭を掻きながら笑う恵を半眼で睨んで、「とにかくそういうことだから、以上。おやすみ」と幸子は話を切り上げた。恵は嬉しそうに「はあい、おやすみ」と返事をしてさっさと出て行ってしまった。
本当は、さっきの兄の態度のことについて相談したかったのに、まるでうまくいかない。幸子は口をとがらせて、これ以上進まない勉強をあきらめるためにシャープペンシルを放り投げた。
「…………」
キッチンで、兄と兄の“友人”である律人(りつと)が並んで食事の準備をしている。幸子の目には二人がとても楽しそうに見える。
(あと、なんか、距離が近い)
福士は身長が高く一八〇センチあったが、律人もそれに匹敵するほどの身長だった。体格も近く、しかし髪型はマッシュショートに近い福士と違ってさっぱりと短く刈り上げている。
(ユズの好きな俳優に似てる……)
自身の友人が雑誌片手に熱く語っていたのを思い出しながら、幸子はリビングのソファでじっと二人の様子を眺めた。
「ふく、きのこどうする?」
「きのこ、さっちゃんが好きだから入れるよ」
「へえ、幸子さん、偉いね。ちゃんときのこ食べれるんだ」
不意に律人に話しかけられて、幸子は慌てて頷いた。律人は福士を肘で小突きながら「ふくと違って」といたずらっぽく笑っている。幸子から少し離れて床に体育坐りをしている幽霊の恵が、『ふーくんまだきのこだめなんだ……』とぼやいた。恵にそこにいてほしがったのは幸子だった。
兄の友人関係は、幸子にとってはわからないもののひとつだった。小学校のころはまだしも、中学校に上がればますます距離が開き、高校はいよいよわからない――わからないうちに、兄はバイトに打ち込むようになってしまったから。
だから、幸子は、あんなに楽しそうで、あんなに嬉しそうな福士の顔をほとんど見たことがなかったように感じた。
『へへ、律人くん、ふーくんと仲良くしてくれて嬉しいな』
恵は体育坐りのまま、ゆらゆらと左右に揺れている。幸子はそれに返事をしなかったが、福士と律人の様子を見ていると、恵の気持ちもわかるような気がする。
二人はときおり、小声で何か会話して、二人だけで楽しそうに笑う。福士が律人の耳許で何かささやき、律人の口が「ばか」と動いた。
「…………」
幸子はむうっと口をとがらせる。なんだか面白くない。
急にソファから立ち上がった幸子に、恵が気づいた。
『さっちゃん、どしたの?』
「一回部屋戻る。できたら呼んでー」
「ん、わかった」
「幸子さん、ゆっくり休んでて」
『え』
大股でリビングを出て階段を上る幸子の後ろから、おろおろと幽霊の恵がついてくる。
『さっちゃん、なんかあった? なんだか、むかむかしてない……?』
「一人にして」
『う。……わかった』
恵はすっといなくなる。わずかに大きな音を立てて部屋の扉を閉めた幸子は、勢いよくベッドに倒れ込んだ。
目をぎゅっとつむると、先ほどの兄と兄の“友人”の様子がどうしても思い出される。楽しそうで、嬉しそうで、なんだか、幸せそうで……
(面白くない!)
心のなかで幸子は叫んだ。こんなふうな気持ちになるのは、幸子にとっては初めてのことだった。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
46 followers · 940 posts · Server nattois.life【使用したお題】
ホットケーキ、ラジオ体操、ゲームをする
「実際さあ、運動ってします?」
突然、六つ下の後輩、堀江にそう訊かれ、私は首を振った。堀江は「ですよねえ」と即座に返してくる。
「インスタでつながってる人とか、結構みんなしてるんすよ。ジム行ったとか平気で言うし……すごくないすか、それ」
「いやすごいよ、すごいと思う」
実は私がSNSでつながっている人たちも、なかなかの頻度で「ジム行った」をはじめ何らかの「運動をしました」報告をしてくる。私はそれをタイムラインで横目に眺め、ゲームをする日々だ。そういえば「フィットボクシングやった」なんて人もいたな。世の中の人たちはすごすぎる。
「こないだの健康診断で問診のときに看護師の人に『運動……どうしてもやる気になりませんかー』とか言われちゃって」
「ワハハハ何言われてんだ」
「三ない運動やってるんで」
酒飲まない、タバコ吸わない、運動しない。指を折り折りそう数える堀江に私の笑いはますます大きくなる。堀江もひとしきりケタケタ笑ってから、半端になっていた弁当を掻き込んだ後に「ほんでえ」と続けた。
「ラジオ体操やるのっていいと思うんすよ」
やや前のめりになってそう訴えかけてくる堀江に私も、なるほどなあ、と頷く。
「そういや藤原商事さんで朝ラジオ体操やってるとか言ってたな。それ聞いたときはまだ二十代とかだったからめんどくせー会社だなと思ってたけど、この歳になってみると……」
「ね! わかりますよね!」
絶対したほうがいいんすよ、と膝をパアンとしたたか打った堀江は、「社長に言ってみようかな」なんてぼやいている。いいんじゃないの、と私もうなずいた。堀江のこういう性格が、“緩い”と“だるい”でぐだぐだになっているこの会社の空気を換えてくれるような気がした。
翌日から朝礼が終わったあとにラジオ体操をやることになったのには驚いた。こいつ、行動力のかたまりすぎる。多分、部署の他の連中も堀江に対してそう思っていて、そして自分自身に対して運動不足を痛感していたのだろう。ラジオ体操をやる習慣は我が社にすんなりと受け入れられた。
「みはるさんちのホットケーキにサツマイモって入ってました?」
堀江の質問はいつもこんなふうに唐突だ。私は首を振る。そもそも我が家ではホットケーキが作られたことがない気がする。
「やっぱそうすか」
「や、ていうか、ホットケーキ食べたことない、多分」
「あ、へー。そっちか」
ふんふんと頷きながら堀江は大きな口で弁当をばくばく食べる。いつも思うけど一口が大きいな。
「彼女がサツマイモもらったからホットケーキに入れてい? て訊いてきて。ホットケーキにサツマイモ入んの!? てびっくりしたんすよ」
「ほー。……え、彼女いたの?」
私の驚きはそっちだった。堀江はぱちぱちと瞬いて「いますよ」と何の気なしに言った。いや、知らんかったからこっち。
「てか、女同士……」
「え? 別にフツーでしょ」
「いや、私の身近では初めてかな……」
「あれ、そうすか」
堀江に「へー意外」みたいな表情をされているのが釈然としないが、私のなかにはもうひとつ疑問が浮かんでいて、どうしてもそちらを優先したくなってしまった。
「ところでホットケーキとパンケーキの違いって何?」
「薄さじゃないんすか?」
「ええ? だってこんくらいふくらんだやつもパンケーキって言うじゃん」
「そういや確かに」
調べるか、とすぐに堀江はスマホを取り出す。こういうすぐにアクションを起こせるところがすごいなあといつも思っている、口にはしないが。堀江はスマホの画面上に忙しなく目線を動かしたあと、「あー」と胡乱な声を発した。
「何?」
「ホットケーキはパンケーキの一種ってことらしいす」
「はあー、なるほど」
何度もうなずく私に、堀江もうなずいてスマホをテーブルに伏せて置く。そこで、私はもうひとつの疑問を訊ねた。
「サツマイモのホットケーキ、おいしかった?」
「そりゃもう。世の中のシャレオツな店はみんなあれを秋の定番にしたほうがいい」
堀江はぱっとスマホをひっくり返してロック画面を見た。たかたかと操作して私に画面を向けてくる。きれいに三角に切られて黄色い断面が撮影されたホットケーキの写真だった。
「あ、これはうまそう」
「ね。今度作ってもらって会社持ってきますよ」
「あら。ごちそうになります」
おどけるように両手を合わせて軽く振ると、堀江は満面の笑みで大きくうなずいた。それを見ただけで、マジでおいしかったんだなあ、と感じられる。
「だからってこれは量多すぎ」
部署の全員に、という前提で持ってこられたサツマイモホットケーキは六号サイズが三枚あって、部署の人数の七人で割り切れもしないし、堀江は一枚を四等分で切ってるしで散々だった。
「ちなみに一枚は自分で焼いて失敗したやつなんで」
「おい」
「裏側見たらわかっちゃうんで。裏側見ないで引いてください」
「ジョーカーの言い方すんな」
同僚たちがあーだこーだ言いながら楽しそうにサツマイモホットケーキの乗った紙皿を取っていく。なぜか裏側が丸焦げのジョーカーを引いたのは私だけで、堀江の心底楽しそうな大笑いが憎らしく、それでいてなんだかおかしくて、私は初めてのホットケーキを文句を言いながら完食した。
「よし、また持ってきますね」
「加減を覚えろ」
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
64 followers · 1584 posts · Server nattois.life――臍からスイカの芽がでちゃった!
――へそから すいかの めが でちゃった!
雲母、神霊と共に
きらら、しんれいと ともに
生きる少女は自分の
いきる しょうじょは じぶんの
臍の芽に困惑した。
へその めに こんわくした。
少女には思い当たる
しょうじょには おもいあたる
ことがあった。
ことがあった。
光のスイカなるもの、それを
ひかりの すいかなるもの それを
タニグク商会なる
たにぐくしょうかいなる
通販を使って
つうはんを つかって
買って食べ、種ごと飲み込んだ。
かって たべ、たねごと のみこんだ。
『その通販を人間が使うには
『その つうはんを にんげんが
使うには 危ないことも
つかうには あぶないことも
あるから、よくよく気をつけて
あるから、よくよく きをつけて
くださいね』
くださいね』
と神霊の佐原桐弘から
としんれいの さはらきりひろから
口を酸っぱくして
くちを すっぱくして
警告されたのにも
けいこくされたのにも
関わらず、守らなかった。
かかわらず、まもらなかった。
「そういうところですよ、
「そういうところですよ、
雲母ちゃん」
きららちゃん」
雲母が佐原桐弘に
きららが さはらきりひろに
相談したところ、そう、眉を
そうだんしたところ、そう、まゆを
顰めて言われた。
しかめて いわれた。
その後、あんまりに言うことを
そのご あんまりに いうことを
聞かないものだから、と、
きかないものだから、と、
怒って口をきかなかった。
おこって くちを きかなかった。
それを見兼ねた雲母の
それを みかねた きららの
友人がいた。
ゆうじんが いた。
雲隠紫蘭だ。
くもがくれ しらんだ。
紫蘭の透視神術に
しらんの とうししんじゅつに
よる分析によると、こうだ。
よる ぶんせきに よると、こうだ。
「光のスイカは元々、
「ひかりの すいかは もともと、
オナモミのように動物に
おなもみの ように どうぶつに
運ばれて数を増やす。
はこばれて かずを ふやす。
だからこそ、哺乳類の
だからこそ、ほにゅうるいの
臍を通じて数を増やす
へそを つうじて かずを ふやす
ように、なったのではないか。
ように、なったのではないか。
だから、今のところは、
だから、いまのところは
幸運にも命に
こううんにも いのちに
別状はないが、念のため、
べつじょうはないが ねんのため
スイカの株の移植の
すいかの かぶの いしょくの
必要はある」
ひつようはある」
そんなこんなで、紫蘭から
そんなこんなで しらんから
頭を下げて
あたまを さげて
頼みこんだところ、
たのみこんだところ、
佐原桐弘は苦笑いした。
さはらきりひろは にがわらいした。
「香香背男、相変わらず
「かかせお、あいかわらず
人間に甘いですね、
にんげんに あまいですね
雲母ちゃんで無ければ、
きららちゃんで なければ、
放置のつもりでした。
ほうちの つもりでした。
これも、本来は人間への
これも ほんらいは にんげんへの
罰として作らました。
ばつとして つくられました。
雲母ちゃんにも知っていて
きららちゃんにも しっていて
嘘をついたのでしょう」
うそを ついたの でしょう」
香香背男と呼ばれた神霊は
かかせおと よばれた しんれいは
静かに頷いた。
しずかに うなずいた。
「吾も、人間にはもっと
「おれも にんげんには もっと
残酷な罰を与えるべき
ざんこくな ばつを あたてるべき
とは思う、けど」
とはおもう、けど」
紫蘭はもう一度、深く
しらんは もういちど、ふかく
深く頭を下げた。
ふかく あたまをさげた。
佐原桐弘は、こう返した。
さはらきりひろは、こうかえした。
「一週間、待ってくださいね」 「いっしゅうかん まってくださいね」
桐弘は自分の身内の
きりひろは じぶんの みうちの
農業神を頼った。
のうぎょうしんを たよった。
無事、雲母の臍から出た
ぶじ、きららの へそから でた
スイカの株を、家庭菜園に
すいかの かぶを かていさいえんに
移すことができた。
うつすことができた。
やがて、スイカの花が咲く。
やがて すいかの はなが さく。
夜もなお、花火のごとく、光る花。
よるもなお はなびのごとく ひかるはな。
「できたスイカ、どうするんですか?」
「できたすいか どうするんですか?」
桐弘は暫く雲母の
きりひろは しばらく きららの
その質問に面を食らっていた。
そのしつもんに めんを くらっていた。
そして、こう返した。
そして こうかえした。
「うーん。お中元にしますかね」
「うーん。おちゅうげんに
しますかね」
そうして、桐弘は神霊の
そうして、きりひろは しんれいの
知り合いにスイカを
しりあいに すいかを
送り付けることとした。
おくりつけることと した。
タニグク商会経由で、
たにぐくしょうかいけいゆで、
そのスイカが送られたのは
そのすいかが おくられたのは
いうまでもない。
いうまでもない。
スイカを贈られた
すいかを おくられた
そのうちの一柱、真朱
そのうちの いっちゅう、まあか
豊は、便箋に目を見開く。
とよは、びんせんに めをみひらく。
――嘘じゃろ。
――うそじゃろ。
豊は、その文面を
とよは、その ぶんめんを
二度見する。
『私、矢野雲母が
『わたし、やのきららが
間違って食べてしまったせい
まちがって たべてしまったせい
で、スイカができました。
で、すいかが できました。
私の臍から生まれた
わたしの へそから うまれた
スイカです。佐原桐弘さんと
すいかです さわら きりひろさんと
株に移した後、
かぶに うつした あと、
責任を持って育てました。
せきにんを もって そだてました。
よかったら食べてください
よかったら たべてください
矢野雲母』
やのきらら』
スイカは神霊の皆様が
すいかは しんれいの みなさまが
おいしくいただきました。
おいしく いただきました。
バラエティ番組みたいな
ばらえてぃ ばんぐみ みたいな
オチになりましたとさ。
おちに なりましたとさ。
羽ペン · @goodquillpen
46 followers · 785 posts · Server nattois.life【使用したお題】
一週間、光の花が咲く(不変の○○(○○は変換可能)も入れたつもりになりたい…)
駒木琴子(こまぎ・ことこ)は緊張していた。今日は町の大きなホテルで開催される花火大会で彼女が初めて手掛けた花火が夜空に打ち上がる日で、彼女が恋する相手、坂出夏(さかいで・なつ)にもその連絡していたから。しかし夏には男性の恋人がいて、このところは琴子と会うよりも恋人を優先しがちになっていることに琴子自身も気づいていたから、そいつと一緒に見に来られるくらいなら見てもらえないほうがマシだ、とギリギリまで粘って、結局連絡をするのが当日の一週間前になってしまった。
[今度の晴嵐の花火で私が作った花火が上がります。言うのギリギリになっちゃったから、もし余裕あったら見に来てよ]
カレシとでも、の一言を入れることは琴子のプライドが許さなかった。メッセージへはすぐに既読マークがつき、
[えーほんと!行く行く!晴嵐って駐車場大きいよね?]
と返事が来て、琴子はぎゅうと唇を引き結んでひとつうなずいた。
[あの坂のところ脇全部駐車場だから急いで来なくても大丈夫だと思う]
[いいところで見たいからすぐ行く!ことこには会えるの?]
[準備と撤収があるから無理かも]
[え~残念。楽しみ!がんばってね!]
投げキッスのスタンプと、おやすみのスタンプが立て続けに送られてきて、琴子もそれにおやすみのスタンプを返して布団に転がる。じたばたしたくなったが抑えた。彼女が暮らしているのは案外振動が伝わりやすいアパートなのだ。
本番当日までの一週間、琴子はそれまで以上に真面目に作業に取り組んだ。春にこの企業に入社して、先輩熟練者から星の作り方を学び、「お前な切り星作んなだば上手だおんだの」と感心したように褒められた。琴子は何かを同じ大きさに切りそろえるのが昔から得意だった。
夏季の花火大会ラッシュはとにかく先輩熟練者のサポートで東奔西走した。そして秋、ついに琴子にとってのデビューのときが来たのだ。
当日は夏から送られてきた[着いたよ。見てます]というメッセージとホテル晴嵐の屋根の写真にがんばるのスタンプを送り返すだけで精いっぱいだった。会社での最終確認作業も行い、現場での点火器の最終チェックも目をかっと見開いて取り組んだ。
そうして暗い夜に打ち上がった、自身の初めて手掛けた花火を見たとき、琴子の目からは自然と涙がこぼれていた。
「がんばったの」
「いい感じだよ、よかったね」
「…………はい゛…………」
先輩の熟練者や幹部から口々に激励の言葉をかけられながら、琴子は奥歯を噛み締めて涙をぬぐった。
そうこうしている間に花火大会は終わり、ホテル晴嵐のスタッフから感謝の言葉を送られながら撤収作業をしていた琴子に先輩熟練者の一人が声をかけてきた。聞けば、友達があっちで待ってる、と言う。
「行ってきていいよ。今日はお疲れ様だったからね」
帰るときには戻ってきてよね、と満面の笑みで見送られた琴子がホテル晴嵐のスタッフ駐車場の入口で見つけたのは、街灯の下に一人で所在なげに立っている夏の姿だった。
「夏!」
「あ、ことこー。お疲れ様。見てたよ! すごかったね!」
夏はまるで我が事のように体を弾ませて喜んで、そのことが琴子の心をぬくめる。ウン、と琴子がうなずくと、「でも、どれがそうなのかはわかんなかったや」と夏がしょんぼりとした様子で言った。
「これかなあって思うのはあったんだけど」
「え、あったの」
「あったよ。高校のときのさあ美術の授業で、ことこが『光の花』ってタイトルで出した絵あったじゃん。あれに似てたから」
琴子はそれを聞いて息が詰まりそうだった――まさに彼女はそれを思い描いて今回の星を作り、その先へ行きたいがために花火師を志したのだから。
「あたしあの絵好きだったから。高校のときも好きって言ったでしょ?」
「え……覚えてない」
「うそお! めっちゃ言ったじゃん! ひどー!」
夏はぱあっと笑顔になって琴子を小突いた。琴子も苦笑を返しながら、はたと思い至った事実に気づく。
「あ、そういえば、彼氏は。待たしてるの?」
「え? ううん。一人で来たよ」
ぱちりと琴子は瞬く。夏は街灯の下にくしゃりといたずらな笑みを浮かべて、「ことこの花火はあたしだけのものにしたかったの」と言いながら肩掛け鞄のショルダーベルトを握った。
「多分、あたしだけのものになったよね?」
伺うような瞳に光の花がきらりと咲く。
「…………なったよ」
絞り出すような声が琴子の喉から出て、街灯の下で己の顔が真っ赤になっていやしないかと彼女は不安になる。それでも、目の前で夏が嬉しそうに笑うのを見ることができた事実を思えば、次に咲かすのはこんな熱でありたい、と琴子の心のなかの種がまたひとつ、密やかに芽生えるのだった。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
46 followers · 744 posts · Server nattois.life【使用したお題】
○○の絆、初夏、慣れてきた?、困難に打ち勝つ
(対決もある意味入れたつもりになりたい)
僕の右腕がなくなり、義手を装着するようになってから初めての夏が来た。まだ完璧な義手ではなくてこれからどんどん改良を重ねていくためのプロトタイプだ。主治医の先生は「この義手では夏は暑くて汗をかくから大変ですよ」と、「少しでも気になることがあったら私のところに来てくださいね」と何度も何度も念押しをしてくれた。僕も何度もうなずいた。
僕や他の人たちの身に起こった事故は町じゅうの知るところとなっていたし、僕の右腕がないことも、僕が義手を使い始めたこともすっかり周知の事実だったけれど、僕を見てくる視線のなかには少なからず僕にとっては嫌だと感じるものも多くて、僕は夏だけど腕を覆うような冷却カバーをつけることにしている。僕らはみんな直射日光にはそんなに強くないけど、仕組みとして体内に冷却装置はしっかり備わっているし、肌が高熱にならないようなシステムが入っている子も多かった。でも残念ながら僕はそうじゃない。義手のためにお金を貯めなくちゃいけないから少しでも節約できるところはしないと。
「もう慣れてきた?」
昼休みのごはんを終えて、雑談を始めた隣の席のカデルに訊かれる。どう返事していいのかもわからず僕はウーンと唸った。それを聞いていた前の席のトリアンが振り返って言う。
「そんな簡単には慣れないよねえ」
「ウーン……ていうか、ときどき勝手に動く」
僕は二人に右腕を見せた。薄橙色の親指がけいれんしているみたいに震える。二人は「これ勝手に動いてるの」と心底驚いたようだった。
「なんでかな」
「さあ……」
あいまいに言葉を濁したけれど、僕はこの義手を紹介されたとき「前の記憶があってもしかしたら制御が効かなくなることがあるかもしれない」と言われたことは、特にトリアンには黙っているべきだと思ってそれ以上は口にしなかった。トリアンの家は“そういう”お宅なのだ、とおばあちゃんが言っていた。
カデルは自分の銀色の腕を曲げたり伸ばしたり、上下左右に好き勝手に動かしながら、「自分の腕が自分でうまく使えないって、不思議だ」と言う。僕はうなずく。うなずくけれど、何も言えない。
そのうちお昼休みも終わりに近づいて、移動教室のための準備が始まった。
「そういえばラゼは退院したのかな」
「もうすぐって言ってなかったっけ?」
カデルとトリアンはそんな会話をしながら僕の前を歩く。そのうち校内掲示板のある壁に差し掛かって、僕はふと足を止めてそれを見た。こないだ発行されたばかりの校内新聞が掲示されていた。
最近はずっと、一番下の段は“あの事件”を受けて作られた“団結”だとか“生徒の絆”だとかの大切さを謳った広告スペースになっている。
『困難に打ち勝とう、私たちにはそれができる』
指向性のスピーカーから聞こえてくる文句が僕の聴覚機構を震わせる。右腕の義手がじとりと汗ばんだ感覚があった。僕は右肘の連結部分を左手で掴む。
『つなごう、オーラリア中学の絆』
「スラト、どしたの」
立ち止まっていた僕をカデルとトリアンが引き返して迎えに来てくれた。二人の顔の真ん中についている目が心配そうな色を帯びる。僕は首を振って歩き出した。薄橙色の右腕を冷却カバーを伸ばして隠す。
この義手にしなきゃよかった、と何度も何度も思う。そのたびこいつは僕の銀色の胸をひっかこうとするけど、そこにコアがないことにはまだ気づかない。もしかしたら時間の問題かもしれないけど、そのころにはきっと新しいタイプのものに変わっているだろうから気にしないことにした。本体は僕なのだ、僕のほうが強い。
不意に、ギュイン、と右肘の連結部分が動いて、僕の太ももをカバーに覆われた義手が打った。痛みは感じない。僕はそれを見下ろして、それから前を向く。やる気をなくしたみたいにだらりと垂れ下がっている右腕にコアのなかで呼びかける。そんなことをしても痛いのはお前のほうだ。僕じゃない。
今日の帰り、先生のところに寄ろう。
僕はそう決めると、カデルとトリアンを追って廊下の角を曲がった。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
63 followers · 1660 posts · Server nattois.life「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
司会者が出題の
しかいしゃが しゅつだいの
合図を出す。
あいずを だす。
イントロ流れるが、いかや、
いんとろながれるが、いかや、
早押し対決。
はやおしたいけつ。
まだ高校生の彼男が
まだ こうこうせいの かのだんが
回答権を、得る。
かいとうけんを える。
「はい!〜」
「はい!〜」
新人アイドル、五十村は、
しんじんあいどる いそむらは
アニメの主題歌の名前を
あにめのしゅだいかの なまえを
なんとか答える。
なんとかこたえる。
アイドルのお仕事の中には、
あいどるの おしごとの なかには、
ドラマの番宣のバラエティもある。
どらまの ばんせんの ばらえてぃも ある。
それがこのイントロQだ。
それが このいんとろ きゅうだ。
流石にクイズ番組は
さすがに くいずばんぐみは
勉強しないとうまく
べんきょうしないと うまく
活躍できないので、
かつやくできないので、
流石の五十村でも
さすがの いそむらでも
慣れずに骨が折れる。
なれずに ほねが おれる。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
司会者の合図。
しかいしゃの あいず。
回答権を得るは、KAWA11Ωの
かいとうけんを えるは かわいいおめがの
メンバー、弓取梓。
めんばー、ゆみとりあずさ。
「はーい、〜」
「はーい、〜」
少し緩やかな声は、
すこし ゆるやかな こえは、
五十村の知らない深夜
いそむらの しらない しんや
アニメの曲名を答える。
あにめの きょくめいを こたえる。
五十村の脳裏に紫蘭の
いそむらの のうりに しらんの
アドバイスが思い出される。
あどばいすが おもいだされる。
――アニソンは梓が取る
――あにそんは あずさが とる
けど他の曲は取れるはず。
けど ほかのきょくは とれるはず。
梓対策ならアニソン必須。
あずさたいさく なら あにそん ひっす。
でもアニソンはみんな知らない
でも あにそんは みんな しらないから
得点の稼ぎどころ。
とくてんの かせぎどころ。
でも、今はゲーム音楽のが
でも、いまは げーむおんがくが
マイナーだから こっちかな。
まいなーだから こっちかな。
そう、塾の先生風に言われた。
そう、じゅくの せんせいふうに いわれた。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
次の曲も梓が取る。
つぎの あずさが とる。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
その次も梓が取る。
そのつぎも あずさが とる。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
今度は別のチームが取る。
こんどは べつの ちーむが とる。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
また梓が取る。司会に注目される梓。
また あずさがとる。しかいに ちゅうもくされる あずさ。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
今度は五十村が回答権。
こんどは いそむらが かいとうけん。
「この曲は、KAWA11Ωさん
「このきょくは かわいいおめがさん
の〜!」
の〜!」
五十村は答える。
いそむらは こたえる。
そう、紫蘭の助言には、
そう しらんの じょげんには、
KAWA11Ωの曲のイントロは
かわいいおめがの いんとろは
わかっとけ、爪痕残せるから、
わかっとけ つめあと のこせるから、
とあった。予想通り。
とあった。よそうどおり。
司会も五十村を注目する。
しかいも いそむらを ちゅうもくする。
――ここからだ。
――ここからだ。
プレッシャーはあった。
ぷれっしゃーは あった。
イントロQは、最後の一曲で
いんとろきゅうは さいごの いっきょくで
梓のチームと五十村のチームの
あずさのちーむと いそむらのちーむの
一騎打ちとあった。司会の合図。
いっきうちとなった。しかいのあいず。
「イントロ〜Q!」
「いんとろ〜きゅう!」
回答権は梓。
かいとうけんは あずさ。
――負けた、と五十村は思った。
――まけた と いそむらは おもった。
「は〜い」
「は〜い」
少し疲れたのか、気怠げさを
すこしつかれたのか けだるげさを
隠しながら、答える梓。
かくしながら こたえる あずさ。
「え?」
「え?」
その音に五十村は耳を疑った。
そのおとに いそむらは みみを うたがった。
心臓が高鳴る。
しんぞうが たかなる。
ブブーと、間違いのサウンド。
ぶぶーと、まちがいのさうんど。
「回答権は、〜の五十村くん!」
「かいとうけんは 〜のいそむらくん!」
司会の指示。
しかいの しじ。
更に、心臓が高鳴る。
さらに、しんぞうが たかなる。
「え、ええと〜」
「え、ええと〜」
五十村は慎重に答える。
いそむらは しんちょうに こたえる。
今度は正解であった。
こんどは せいかいで あった。
五十村のチームが優勝。
いそむらの ちーむが ゆうしょう。
――勉強した甲斐があった。
――べんきょうしたかいが あった。
五十村はホッとしていた。
いそむらは ほっとしていた。
放送後、紫蘭から祝いの
ほうそうご しらんから いわいの
メールが来た。
めーるがきた。
『反射神経がすげぇ!
『はんしゃしんけいが すげぇ!
だから、吾と反射神経対決する?』
だから おれと はんしゃしんけい たいけつする?』
五十村は
いそむらは
『神様と反射神経
『かみさまと はんしゃしんけい
対決は無茶です』
たいけつは むちゃです』
と返信するしかなかった。
とへんしんするしかなかった。
流石に、ね。
さすがに、ね。
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
#一次創作
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
63 followers · 1659 posts · Server nattois.life※肉食描写あり
※にくしょくびょうしゃあり
深夜、ホテル内のコンビニ。
しんや ほてるないの こんびに。
伊鶴は、息を上げながら
いつるは いきを あげながら
自動ドアをくぐる。
じどうどあを くぐる。
――ここなら、追っかけも来ない。
――ここなら おっかけも こない。
でも、追っかけやマスコミを
でも おっかけや ますこみを
追い返すように走ってきたの
おいかえすように はしってきたの
だから、伊鶴の全身は
だから、いつるの ぜんしんは
汗でびしょ濡れだ。
あせで びしょぬれだ。
息を付く間もなく、目を
いきを つくまもなく めを
見開きながら、伊鶴は汗を拭う。
みひらきなから いつるは あせをぬぐう。
「――雲母?!」
「――きらら?!」
ケンカしたはずの同僚が、
けんかしたはずの どうりょうが
眼の前にいた。
めのまえに いた。
「あ、伊鶴」
「あ、いつる」
雲母はレジの肉まんやあんまんを
きららは れじの にくまんや あんまんを
物色していた目線を、伊鶴に移した。
ぶっしょくしていた めせんを いつるに うつした。
「さっきの、お父さんのこと、
「あ、さっきの おとうさんのこと
ごめんなさい」
ごめんなさい」
アイドルの同僚は頭を下げる。
アイドルのどうりょうは あたまを さげる。
気遣いの雲母にしては珍しく、
きづかいの きららにしては めずらしく
不用意に父のことを
ぶよういに ちちのことを
無理矢理聞いたので、
むりやりきいたので、
伊鶴が不機嫌になって
いつるが ふきげんになって
ブチ切れてしまったのだ。
ぶちきれてしまったのだ。
「紫蘭との隠し事のあれこれでしょ」
「しらんとの かくしごとの あれこれでしょ」
冬の歌謡祭も近づいている中、
ふゆの かようさいも ちかづいているなか、
伊鶴はソワソワしていた。
いつるは そわそわしていた。
父に関わる大きな何かが
ちちに かかわる おおきな なにかが
崩れ去ろうとしていた。
くずれさろうと していた。
それに裏から雲母と紫蘭が
それに うらから きららと しらんが
魔術的に関わっている。
まじゅつてきに かかわっている。
だから、アイドルであった父の話は、
だから、あいどるであった ちちのはなしは
雲母と我らが家庭教師、
きららと われらが かていきょうし、
紫蘭にとっては超重要事項だ。
しらんにとっては ちょうじゅうようじこうだ。
そう分かっていても、父にも伊鶴にも
そう わかっていても ちちにも いつるにも
辛い話ばかりなので、
つらいはなしはがりなので
紫蘭がいないと、
しらんが いないと
こうしてケンカ腰になってしまう。
こうして けんかごしに なってしまう。
まあ、紫蘭がいると、
まあ しらんが いると
緊急時の姿といつもの姿と
きんきゅうじの すがたと いつもの すがたと
雰囲気が全然違うから、
ふんいきが ぜんぜんちがうから
何かやってるんだろうなと
なにか やってるんだろうなと
伝わりやすいからだ。
つたわりやすいからだ。
最低ながら、こちらの心象の問題だ。
さいていながら、こちらの しんしょうの もんだいだ。
雲母に言うと、紫蘭が
きららにいうと しらんが
偶像であるからよ、
ぐうぞうで あるからよ、
と否定するけど。
と ひていするけど。
そう、伊鶴は思い返していた。
そう いつるは おもいかえしていた。
「あの、あんまん2つ!」
「あの、あんまんふたつ!」
雲母は財布のがま口を
きららは さいふの がまぐちを
広げながら店員に頼む。
ひろげながら てんいんに たのむ。
――雲母、よく私があんまん好きなの覚えているな?!
――きらら よく わたしが あんまんすきなの おぼえているな?!
感心する伊鶴。
かんしんする いつる。
コンビニ店員は慣れた手付きで
こんびにてんいんは なれたてつきで
あんまんを包む。
あんまんを つつむ。
「ありがとう、後で払うよ」
「ありがとう あとではらうよ」
伊鶴が申し出ると、
いつるが もうしでると
雲母はこう返す。
きららは こうかえす。
「わかった。そういえば、なんで
「わかった。そういえば、なんで
あんまん、好きなのかなあって」
あんまん、すきなのかなあって」
「父さん、あんまん好きだったんだよね」
「とうさん あんまん すきだったんだよね」
蒸した饅頭の匂いを
むした まんじゅうの においを
吸い上げながら、伊鶴は父の話をする。
すいあげながら いつるは ちちのはなしを する。
――かつての父さんみたいに、
――かつての とうさんみたいに
マスコミに守られたかったなあ。
ますこみに まもりたかったなあ。
ふと、伊鶴は思う。
ふと いつるは おもう。
「そう、お父さんとの思い出
「そう おとうさんとの おもいで
なんだね」
なんだね」
あんまんを一口食むと、
あんまんを ひとくち はむと
雲母はまた口を開く。
きららは また くちを ひらく。
「守られていてもその中で
「まもられていても そのなかで
潰されて蹴落として
つぶされて けおとして
息苦しいのも、よくないもの。
いきぐるしいのも、よくないもの。
もっと、いい守り方があるじゃない」
もっと、いいまもりかたがあるじゃない」
雲母は、どこかを見据えている
きららは どこかを みすえている
ようにも見えた。
ようにも みえた。
――ああ、アイドルとして
――ああ あいどるとして
どういう明日を辿るのだろう。
どういう あすを めぐるのだろう。
そのどこかを伊鶴は見ようと
そのどこかを いつるも みようと
手を伸ばした。
てをのばした。
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
羽ペン · @goodquillpen
44 followers · 660 posts · Server nattois.life【使用したお題】
添い寝、偉大な力(ニュアンス)
五日ごとの休沐のたびに李周(り・しゅう)が向かうのは、長江に沿ってなだらかに伸びる丘だった。彼はその丘のふもとに小さな庵を建て、家人も雇わずもう二十年も一人で暮らしている。同僚などは彼を案じてか、あるいは奇矯に思ってか、事あるごとに「人を雇わぬのか」「妻を娶らぬのか」と訊ねるが、そのたびに李周は首を振り続け、孤独に暮らす小屋に帰るのだった。
この庵を訊ねてくるものは泥棒以外にはなかったが、この泥棒も荒らすだけ荒らして盗るものが何もないとさっさといなくなる。そのうえ界隈で「あすこには何もない」とでも噂が流れたのか、十年前からは盗みに入られるということもなくなっていた。
余人の目からは何もないように見えるこの庵だが、実際には李周が書き溜め続けている書簡が壁の三方に所狭しと並べられ、天井まで積み上げられてあった。李周は昔から物を覚える力が人よりあって、今彼が熱心に書き溜めているのは、愛すべき友人である胡鉉(こ・げん)が彼のために話して聞かせた物語の数々である。
胡鉉は――李周にとっては――優れた物語の語り部であったが、かの男は文字を読み書きすることがどうしてもできなかった。李周は彼に乞われて何度も字を教えたが、一向に身につかない。そこで李周は「ならば自分が君の代わりに物語を書き留めるよ」と申し出て、胡鉉はそれを大変喜び、様々に思い描いた物語を李周に語って聞かせた。
そうしたことが長く続いていたが、胡鉉はあるとき流行り病に罹ってあっけなく命を落とした。泣き崩れる李周は彼の最期の言葉に従い、太湖と長江とを遥かに望むこの丘のふもとに胡鉉の遺体を埋めたのだった。
胡鉉を喪ってからはしばらく失意に沈んでいた李周であったが、彼の頭にうずまく胡鉉の言葉、物語の数々は決して鳴りを潜めてはくれなかった。
李周は一心に物語を書き記し続けた。休沐の間ひとつも飯を取らぬことも間々あり、五日官庁に籠っている間にこっそりと懐に簡を忍ばせ、庵に持ち帰ることもしばしばあった。幸い誰に見咎められることもなく、今日もいくつかの簡を持ち帰ってきている始末である。
李周の頭のなかで胡鉉は語る。それは自然の物語。それは先祖の物語。それは愛の物語。それは怪異の物語。それは反乱の物語。
「君、もしかして、そのつもりなのかい」反乱の物語を聴いて瞠目した李周に、胡鉉はけらけらと笑って返した。「仲円(ちゅう・えん/李周の字)、そんな怖い顔をしないで。これは物語だよ」そうして、遠い目をした。「おれのなかから生まれた物語だ」
李周の体内でそれは渦を巻く。庵じゅうを文字が舞う。正面の入口の他は窓もない、薄暗い庵いっぱいに物語が満ちていく。
いつか、胡鉉の家で二人中庭を眺めながら、彼の歌うように紡がれた物語に李周は心地よく身を委ねていた。とろりと甘い声で語られるそれは、二頭の虎の逢瀬のことだった。
「おれは虎になりたいな」
胡鉉はよくそんなことを言った。
「そうすれば文字など必要ないしな。あの力で丘をどこまでも駆けて行ける」
「『風は虎に従う』という言葉がある。君なら風を味方につけられるだろうな」
李周は夢見心地にそう答える。うっすら閉じた瞼の向こうで、胡鉉が笑いながら身を捩ったように感じた。
「君がおれの風になってくれよ」
ああ、あのとき、李周はなんと答えたのだったか。
ふ、と気がついたとき、李周は夕暮れの光が射す庵ですっかり横になって眠っていた。腕のなかには読みかけの竹簡がいくつも収まっている。
眠ってしまっていたか。このところはこんなことがよくある。体を起こすのもおっくうで、彼はしばらくもぞもぞと体勢を代えながら寝転がっていた。
腕のなかに竹簡を抱いていると、胡鉉と添い寝をしたいくつもの夜を思い出す。彼の足先の爪の形。足の甲の骨の筋。どの夜も胡鉉は、灯台の火の揺らめきにふさわしい静かな声で李周に物語を語って聞かせてくれ、そうして李周はいつの間にか眠りに落ちていたのだった。
ようやく李周は体を起こす。庵の外から射してくる夕暮れの光は、室内に光の粒を舞い散らせる。木々の葉擦れの音がささやかに聞こえる。穏やかな風が吹いているのだ。
「物語はどこまで行けると思う?」
李周は茫然と、誰にともなく問いかける。
「この風はどこから吹いてきて、どこへ向かって吹き去るのだろう?」
いつしか、李周は自身の頬に伝う涙に気がついた。それは顎からはたり、はたりと床に落ち、散らばっている竹簡を濡らしていく。
困った。墨が滲んでしまうかもしれない。簡が腐ってしまうかもしれない。だが、李周にはこの涙を止めるすべが思い浮かばない。
両手で抱えきれぬほどの数の簡を掻き抱き、李周は足をもつれさせながら庵の外に飛び出た。
広く、偉大な太湖の湖面が西から射す夕闇に輝いているのが遠くに見える。草原が風に揺れている。東から夜が空に満ち、星が小さくとも導きの火を燃やし始める。
李周は声を張り上げて胡鉉の名を呼んだ。何度も、何度も、何度も。
[おわり]
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
62 followers · 1606 posts · Server nattois.life※五月に出る文学フリマ新刊のネタバレ要素しかないです
※ごがつに でる ぶんがくふりま しんかんの ねたばれようそしか ないです
暑っい。あつい。
あつっい あつい。
そんな激しい炎天下の中、
そんなはげしい えんてんかのなか、
日傘をさした集団がいた。
ひがさを さした しゅうだんがいた。
彼女ら、五人の少女が、
かのじょら、ごにんの しょうじょが
墓の前で、手を合わせる。
はかのまえで てを あわせる。
雲母、伊鶴、璃那、梓、琴音。
きらら、いつる、りな、あずさ、ことね。
人気アイドル、KAWA11Ωの
にんきあいどる かわいいおめがの
メンバー全員は、全国ツアー
めんばーぜんいんは ぜんこくつあー
公演の合間に、こうして
こうえんの あいまに こうして
それぞれの先祖の墓参りに
それぞれの せんぞの はかまいりに
行っていた。もちろん任意だ。
いっていた。もちろんにんいだ。
その後ろで、ぐったりと
その うしろで ぐったりと
しなびている人形の有機物と
しなびている ひとがたの ゆうきぶつ
ただの人間が一柱と一人、いた。
ただの にんげんが いっちゅうと ひとり、いた。
「紫蘭、起きろ、起きろったら」
「しらん おきろ おきろったら」
館平は紫蘭を起こした。
たてひらは しらんを おこした。
「むなゃむにゃーふんがー、暑っいあつい、は!」
「むなゃむにゃーふんがー、あつっい あつい、は!」
二人はさっきまで車の中で
ふたりは さっきまで くるまのなかで
添い寝していたのだが、しらんは
そいねしていたのだが、しらんは
ぷかぷかと浮きながらも
ぷかぷかとうきながらも
まだ寝ぼけ気味だ。
まだねぼけぎみだ。
「おにーちゃんお疲れ!お花は
「おにーちゃん おつかれ おはなは
こっちでやっといたから」
こっちで やっといたから」
墓参りから戻る璃那は
はかまいりから もどる りなは
そう言いながら館平にウインクした。
そういいながら たてひらに ういんくした。
館平は目をこする紫蘭に、
たてひらは めをこすれ しらんに
スポーツドリンクを飲ませながら、
すぽーつどりんくを のませながら
日傘をさした。
ひがさを さした。
ただの高校の級友から、
ただの こうこうの きゅうゆうから、
アイドルである妹達の
あいとるである いもうとたちの
ボディガード……
ぼでぃーがーど……
今はこんなにもだらしなく
いまは こんなにも だらしなく
寝惚けているが……となるとは
ねぼけているが……となるとは
つゆとも思わなかった。
つゆとも おもわなかった。
というのも、矢野雲母の
というのも やのきららの
追っかけをやっているのは単純に
おっかけを やっているのは たんじゅんに
妹を厄介ファンから
いもうとを やっかいふぁんから
守るためであって……
まもるためであって……
それがまさか友達の誰かに
それが まさか ともだちの だれかに
バレるなんて予想外過ぎた。
ばれるなんて よそうがい すぎた。
そいつが神霊であるばかりに、
そあうが しんれいで あるばかりに、
秘密はバレてしまったわけだが。
ひみつは ばれてしまったわけだが。
「日傘、いる?って、わ!」
「ひがさ、いる?って、わ!」
突然、雨が降り出した。
とつぜん、あめが ふりだした。
冷たい風も穏やかながら
つめたいかぜも おだやかながら
吹き出した。見上げると、神霊の
ふきだした。みあげると、しんれいの
友人が水を得た魚のように、
ゆうじんが みずをえた さかなのように
墓地の空中を泳ぎ回っていた。
ぼちのくうちゅうを およぎまわっていた。
「環境破壊する誰かさんの
「かんきょうはかいする だれかさんの
お陰で、こうして専門外の
おかげで、こうして せんもんがいの
吾でも雨を呼び出しやすい
おれでも あめを よびだしやすい
のは如何かとは思うけどね」
のはいかがかとは おもうけどね」
紫蘭の呆れ言葉を、
しらんの あきれことばを
館平は、半分だけ嘘だとわかった。
たてひらは はんぶんだけ うそだと わかった。
――大丈夫?暑くない?
――だいじょうぶ?あつくない?
せっかく兄妹水入らずの
せっかく きょうだい みずいらずの
時間が少しでもあるんだったら、
じかんが すこしでも あるんだったら、
目一杯、楽しまないと。
めいっぱい、たのしまないと。
そんな、ささやかなる気遣いが
そんな ささやかなる きづかいが
本心であると、知っていたからだ。
ほんしんであると しっていたからだ。
墓参りをすると、館平は、
はかまいりをすると たてひらは
一目散に妹の方に向かった。
いちもくさんに いもうとのほうに むかった。
それを、紫蘭や雲母らは
それを しらんや きらららは
微笑ましく見守っていた。
ほほえましく みまもっていた。
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
60 followers · 1552 posts · Server nattois.lifeコンテンツワーニング
こんてんつわーにんぐ
※自死表現あります
※じしひょうげん あります
ふと、体を動かしてみる。
ふと、からだを うごかしてみる。
日光、雨水、土地の
にっこう あまみず とちの
匂いが 体全体に
においが からだぜんたいに
飛び込んでくる。
とびこんでくる。
ついでに、人間の辛さも、
ついでに にんげんの つらさも
嘆きも、悲しみも、怒りも
なげきも かなしみも いかりも
飛び込んでくる。
とびこんでくる。
「助……けて」
「たす……けて」
吾は神霊としての
おれは しんれいとしての
神通力故、そういった他の
じんつうりきゆえ そういった ほかの
誰かの声が
だれかのこえが よくきこえた。
今、飛び込んできたそれも、
いま とびこんできた それも、
ある、誰かが生きるか死ぬか、
ある、だれかが いきるかしぬか、
悩み抜いた中の感情だ。
なやみぬいたなかの かんじょうだ。
――ね。
――ね。
吾は、そう、噛みしめるように思う。
おれは そう、かみしめるように おもう。
今すぐすっ飛んでたすけることも
いますぐ すっとんで たすけることも
しようと思えばできるが、
しよう とおもえば できるが
方法によっては
ほうほうに よっては
本人の ためにならないだろう。
ほんにんの ために ならないだろう。
人助けは 本人の意志があってこそ
ひとだすけは ほんにんの いしがあってこそ
なのだから。少し考えないと。
なのだから。すこし かんがえないと。
深呼吸してみる。
しんこきゅうしてみる。
頭皮が風で冷たい。
とうひが かぜで つめたい。
腰まで長い自分の髪が
こしまでながい じぶんの かみが
風に吹き流されているのだ。
かぜに ふきながされているのだ。
――あー、心配だ。
――あー、しんぱいだ。
吾は空に浮きながら
おれは そらに うきながら
腕組みをした。
うでくみをした。
こんな人間、滅ぼしちゃえばいい。
こんなにんげん ほろぼしちゃえばいい。
こんな人間、助け尽くしちゃえばいい。
こんなにんげん たすけつくしちゃえばいい。
ああ、どちらかに転べたら
ああ どちらかに ころべたら
楽なのにな。
らくにのにな。
割とそこそこ「成熟」
わりと そこそこ 「せいじゅく」
した今でも思うのだ
した いまでも おもうのだ。
「あ、紫蘭、どうした?」
「あ、しらん どうした?」
朝顔がホバーボードのように
あさがおが ほばーぼーどのように
箒に乗って話しかけた。
ほうきにのって はなしかけた
心配なときはこうして来てくれる
しんぱいなときは こうしてきてくれる
ことを申し訳なくもありがたく感じていた。
ことを もうしわけなくも ありがたく かんじていた。
「ごめん、ちょっと、
「ごめん、ちょっと、
考え事をしていてね」
かんがえごとを していてね」
吾が自分を誤魔化すのは朝飯前だった。
おれが じぶんを ごまかすのは あさめしまえだった。
「紫蘭の嘘つき」
「しらんの うそつき」
そうふくれっ面で言われた。
そう ふくれっつらで いわれた。
いつも朝顔にはバレバレだ。
いつも あさがおには ばればれだ。
だが、その誰かの「助けて」という声は、
だが そのだれかの「たすけて」という こえは、
飛び降りという形でかき消されされようとしていた。
とびおりという かたちで かきけされようと していた。
寝不足でもないのに
ねぶそくでも ないのに
心臓がバクバクと鳴る。
しんぞうが ばくばくと なる。
吾は、音速より速く飛んだ。
おれは じぇっときのように おんそくよりはやく とんだ。
「やっぱり無理!我慢できねえわ」
「やっぱりむり がまんできねえわ」
「またーこれだから神霊は」
「またーこれだから しんれいは」
しょうがないな、というように
しょうがないな というように
朝顔は苦笑いして見送った。
あさがおは にがわらいして みおくった。
箒で後で追いかけることもあるけど。
ほうきで あとで おいかけることも あるけど。
吾は無我夢中で飛び、
おれは むがむちゅうで とび、
むりやりにその飛び降りた人間を助けた。
むりやりに その とびおりた にんげんを たすけた。
助けてくれる法人などの
たすけてくれる ほうじんなどの
連絡先を教えた。
れんらくさきをおしえた。
「じゃぁ、また」
「じゃぁ、また」
流星のように、吾はそそくさと 飛び去った。
りゅうせいのように おれは そそくさと とびさった。
――ある人間が生きたいのに、それに
――あるにんげんが いきたいのに それに
できる限りでよいのに
できるかぎりでよいのに
答え尽くすことは、なんでこんなに
こたえつくすことは なんでこんなに
難しいのでしょうか?
むずかしいのでしょうか?
それで人が死に続けてもいいのでしょうか?
それで ひとが しにつづけても いいのでしょうか?
無いものねだりなのでしょうか?
ないものねだり なのでしょうか?
吾は、どちらにも転べない天秤を
おれは どちらにも ころべないてんびんを
嘲笑うかのように
あざわらうかのように
泥をすするように
どろを すするように
ただ、ちっぽけな人間をずっと
ただ、ちっぽけな にんげんを ずっと
流星と共に見守るのだろうか。
りゅうせいと ともに みまもるのだろうか。
いや、吾の悩みは、時の流れで解決するのだろうか。
いや おれの なやみは ときの ながれで かいけつするのだろうか。
篠岡遼佳 · @haru_shino
4 followers · 4 posts · Server mstdn.jp時間内でまとまらなかった……。あうあう。
もっとサクサク書ける能力が欲しい。長編を書く時も無駄に長くなるのはこの性質の所為だな……。
【第10回フリーワンライ】
○○の栄養(○○は変換可能)
思い出
タイトル:泥の中の記憶
https://kakuyomu.jp/works/16817330655237513806/episodes/16817330656216421300
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
57 followers · 1516 posts · Server nattois.life※ちょっと危なっかしい表現が入ります
※ちょっと あぶなっかしい ひょうげんが はいります
ある夜。
あるよる。
隠れ家風のレストランの前で、
かくれがふうの れすとらんのまえで
アイドルは姉の運転するレンタカーに乗る。
あいどるは あねの うんてんする れんたかーに のる。
「じゃ!ごちそうさま!」
「じゃ!ごちそうさま!」
銀髪の青年は
ぎんぱつの せいねんは
パートナーの女性と
ぱーとなーの じょせいと
手をつなぎながら
てをつなぎながら
笑顔で手を振る。
えがおで てをふる。
「いえいえ!楽しかった!また!」
「いえいえ!たのしかった!また!」
人気アイドル、矢野雲母は
にんきあいどる やのきららは
パタンと車の扉を締めながら、
ぱたんと くるまの とびらを しめながら
ぞんざい気味に手を振り返す。
ぞんざいぎみに てを ふりかえす。
「雲母、行くよー」
「きらら、いくよー」
姉の石英はレンタカーを走らせる。
あねのせきえは れんたかーを はしらせる。
アイドルを見送り終わった
あいどるをみおくりおわった
青年は、パートナーの顔を
せいねんは、ぱーとなーのかおを
銀色の目でそっと見つめる。
ぎんいろのめで そっとみつめる
「朝顔、送ってくよ」
「あさがお、おくってくよ」
「うん、いつものでしょ、
「うん、いつものでしょ、
危ないから準備しとく。ありがとう」
あぶないから じゅんびしとく。ありがとう」
朝顔と呼ばれたパートナーの女性は
あさがとと よばれた ぱーとなーの じょせいは
どこか嬉しそうに浮足立った。
どこか うれしそうに うきあしだった。
車は、ネオンの多い
くるまは ねおんのおおい
町中を走る。
まちなかを はしる。
だが、身バレ防止のため、
だが、みばれぼうしの ため、
間仕切りで、雲母からは
まじきりで きららから きららからは
車外は見えない。
しゃがいは みえない。
疲れで雲母はウトウトと
つかれで きららは うとうとと
眠りに落ちる。
ねむりに おちる。
成人にとっては、夜は
せいじんに とっては よるは
まだまだこれからが本番か、
まだまだ これからが ほんばんか、
二次会に繰り出す酔っ払いが。
にじかいに くりだす よっぱらいが
ネオンの町中に消えた。
ねおんの まちなかに きえた。
はっ、雲母が目を覚まして
はっ、きららが めをさまして
車から出ると、
くるまから でると
空が少し眩しかった
そらが すこし まぶしかった。
雲母がもしかして、と見上げると、
きららが もしかして、とみあげると、
天空に緩く銀の光が放たれる。
てんくうに ゆるく ぎんの ひかり が はなたれる。
パートナーの朝顔を
ぱーとなーの あさがおを
横抱きにしながら大きく跳躍をする、
よこだきにしながら おおきくちょうやくをする、
元家庭教師の青年。
もとかていきょうしの せいねん。
食事後でジャンプする栄養も
しょくじごで じゃんぷする えいようも
満点だったのであろう。
まんてんだったので あろう。
いや、神術でゆっくり
いや しんじゅつで ゆっくり
空を飛んで イチャイチャ
そらをとんで いちゃいちゃ
デートするカップルがいるか。
でーとするかっぷるがいるか。
いるんだな、空に。
いるんだな、そらに。
「ほんと、あんなに空は飛べないけど、色んなこと、教えてもらったなあ」
「ほんと あんなに そらは とべないけど いろんなこと おしえてもらったなあ」
雲母は光を見て、ふと思い出す。
きららは ひかりを みて ふとおもいだす。
神術で光を出す青年。
しんじゅつで ひかりをだすせいねん。
「ほら、虫眼鏡で黒い紙が……」
「ほら むしめがねで くろいかみが……」
「紙、焼けてる焼けてる!」
「かみ、やけてるやけてる!」
「先生!火事になりますよ!」
「せんせい!かじになりますよ!」
雲母やアイドルグループの
きららや あいどるぐるーぷの
メンバーが口々にいう。
めんばーが くちぐちに いう。
黒い紙はドーナツのように焼け、
くろいかみは どーなつのように やけ、
炎は青年に燃え移ろうと
ほのおは せいねんに もえうつろうと
しているところだった。
しているところだった。
青年は冷や汗をかきながら、
せいねんは ひやあせを かきながら
むりやり火を揉み消した。
むりやりひを もみけした。
雲母は焦げた臭いを吸いつつも、
きららは こげたにおいを すいつつも、
胸を撫で下ろした。
むねを なでおろした。
――はらはらしたな、あの時は。
――はらはらしたな あのときは
お陰で 理科のテストは満点取れたけど。
おかげで りかのてすとは まんてんとれたけど。
苦笑しながら雲母はその流星に手を振る。
くしょうしながら きららは その りゅうせいに てをふる。
そして家の中に入った。
そして いえのなかに はいった。
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負
#一次創作
藤 せっかじん :progresspride_i_flag: · @kasuga768star
57 followers · 1516 posts · Server nattois.life※ちょっと危なっかしい表現が入ります
※ちょっと あぶなっかしい ひょうげんが はいります
ある夜。
あるよる。
隠れ家風のレストランの前で、
かくれがふうの れすとらんのまえで
アイドルは姉の運転するレンタカーに乗る。
あいどるは あねの うんてんする れんたかーに のる。
「じゃ!ごちそうさま!」
「じゃ!ごちそうさま!」
銀髪の青年は
ぎんぱつの せいねんは
パートナーの女性と
ぱーとなーの じょせいと
手をつなぎながら
てをつなぎながら
笑顔で手を振る。
えがおで てをふる。
「いえいえ!楽しかった!また!」
「いえいえ!たのしかった!また!」
人気アイドル、矢野雲母は
にんきあいどる やのきららは
パタンと車の扉を締めながら、
ぱたんと くるまの とびらを しめながら
ぞんざい気味に手を振り返す。
ぞんざいぎみに てを ふりかえす。
「雲母、行くよー」
「きらら、いくよー」
姉の石英はレンタカーを走らせる。
あねのせきえは れんたかーを はしらせる。
アイドルを見送り終わった
あいどるをみおくりおわった
青年は、パートナーの顔を
せいねんは、ぱーとなーのかおを
銀色の目でそっと見つめる。
ぎんいろのめで そっとみつめる
「朝顔、送ってくよ」
「あさがお、おくってくよ」
「うん、いつものでしょ、
「うん、いつものでしょ、
危ないから準備しとく。ありがとう」
あぶないから じゅんびしとく。ありがとう」
朝顔と呼ばれたパートナーの女性は
あさがとと よばれた ぱーとなーの じょせいは
どこか嬉しそうに浮足立った。
どこか うれしそうに うきあしだった。
車は、ネオンの多い
くるまは ねおんのおおい
町中を走る。
まちなかを はしる。
だが、身バレ防止のため、
だが、みばれぼうしの ため、
間仕切りで、雲母からは
まじきりで きららから きららからは
車外は見えない。
しゃがいは みえない。
疲れで雲母はウトウトと
つかれで きららは うとうとと
眠りに落ちる。
ねむりに おちる。
成人にとっては、夜は
せいじんに とっては よるは
まだまだこれからが本番か、
まだまだ これからが ほんばんか、
二次会に繰り出す酔っ払いが。
にじかいに くりだす よっぱらいが
ネオンの町中に消えた。
ねおんの まちなかに きえた。
はっ、雲母が目を覚まして
はっ、きららが めをさまして
車から出ると、
くるまから でると
空が少し眩しかった
そらが すこし まぶしかった。
雲母がもしかして、と見上げると、
きららが もしかして、とみあげると、
天空に緩く銀の光が放たれる。
てんくうに ゆるく ぎんの ひかり が はなたれる。
パートナーの朝顔を
ぱーとなーの あさがおを
横抱きにしながら大きく跳躍をする、
よこだきにしながら おおきくちょうやくをする、
元家庭教師の青年。
もとかていきょうしの せいねん。
食事後でジャンプする栄養も
しょくじごで じゃんぷする えいようも
満点だったのであろう。
まんてんだったので あろう。
いや、神術でゆっくり
いや しんじゅつで ゆっくり
空を飛んで イチャイチャ
そらをとんで いちゃいちゃ
デートするカップルがいるか。
でーとするかっぷるがいるか。
いるんだな、空に。
いるんだな、そらに。
「ほんと、あんなに空は飛べないけど、色んなこと、教えてもらったなあ」
「ほんと あんなに そらは とべないけど いろんなこと おしえてもらったなあ」
雲母は光を見て、ふと思い出す。
きららは ひかりを みて ふとおもいだす。
神術で光を出す青年。
しんじゅつで ひかりをだすせいねん。
「ほら、虫眼鏡で黒い紙が……」
「ほら むしめがねで くろいかみが……」
「紙、焼けてる焼けてる!」
「かみ、やけてるやけてる!」
「先生!火事になりますよ!」
「せんせい!かじになりますよ!」
雲母やアイドルグループの
きららや あいどるぐるーぷの
メンバーが口々にいう。
めんばーが くちぐちに いう。
黒い紙はドーナツのように焼け、
くろいかみは どーなつのように やけ、
炎は青年に燃え移ろうと
ほのおは せいねんに もえうつろうと
しているところだった。
しているところだった。
青年は冷や汗をかきながら、
せいねんは ひやあせを かきながら
むりやり火を揉み消した。
むりやりひを もみけした。
雲母は焦げた臭いを吸いつつも、
きららは こげたにおいを すいつつも、
胸を撫で下ろした。
むねを なでおろした。
――はらはらしたな、あの時は。
――はらはらしたな あのときは
お陰で 理科のテストは満点取れたけど。
おかげで りかのてすとは まんてんとれたけど。
苦笑しながら雲母はその流星に手を振る。
くしょうしながら きららは その りゅうせいに てをふる。
そして家の中に入った。
そして いえのなかに はいった。
#創作版深夜の真剣文字書き60分一本勝負